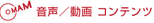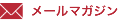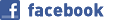1960年代~70年代のメタボリズムの全盛期には、建築や都市計画の分野だけでなく、美術や音楽などジャンルを超えた横断的な活動や交流が活発に行われました。建築が単体の建物から都市のインフラなども包括したメガストラクチャーへと拡張するなか、美術の分野でも表現のための空間は、「環境」あるいは「エンバイロメント」という言葉に置き換えられ、大きく拡張しました。2011年12月18日(日)に開催された「メタボリズムの未来都市展」第5回シンポジウムでは、「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」というテーマで、当時渦中にいた建築家、アーティスト、作曲家、あるいはその時代の研究者や批評家を招き、活発な議論が展開されました。その模様を連載でお伝えします。
連載(1)では、シンポジウムのキーワードにもなっている「空間から環境へ」について、同タイトルで1966年に開催された展覧会を中心に、その美術史上の位置づけを論じていただいた埼玉大学教養学部教授の井口壽乃氏のプレゼンテーションからご紹介します。
メタボリズムの未来都市 関連シンポジウム第5回「空間から環境へ」 2011年12月18日 [出演: 浅田 彰(京都造形芸術大学大学院長)、井口壽乃(埼玉大学教授)、磯崎 新(建築家)、一柳 慧(作曲家、ピアニスト)、山口勝弘(美術家) モデレーター: 片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター)]

埼玉大学教授 井口壽乃さん
撮影:御厨慎一郎
片岡:今回は、「メタボリズムの未来都市展」の最後の関連シンポジウムです。展覧会のなかにある「空間から環境へ」というセクションに関連し、出品作家や建築家、専門家の方々をお招きして、この時代のインターメディアな活動と万博について紹介する機会として企画しました。同時代のインターメディアな活動、あるいは万博については、これまで多くの議論がなされていますが、本日は特に「環境」もしくは「エンバイロメント」という言葉をキーワードに、従来の芸術のカテゴリーから、それぞれはみ出したところに皆さんが求めていた新たなエネルギーの生まれる場というものが何であったのかを、今日的な視点から読み解いていきたいと思っています。
特に、メタボリズム、あるいはメガストラクチャーという概念によって、建築が単体の建築として存在するだけではなくて、都市全体、もしくは環境全体との関係性の中で考えられるようになったことと、当時の、例えば美術の世界におけるジャクソン・ボロックの「アクション・ペインティング」、もしくはアラン・カプローらによる「ハプニングス」、「エンバイロメント」といった概念、それからジョン・ケージに見る「偶然性」などが、極めて興味深い親和性を持っているのではないかと考えています。
本日は5名の方をゲストにお迎えしています。それぞれの方に少し長めにプレゼンテーションあるいはお話しいただき、その後で意見交換ができればと考えています。
建築家の磯崎新さんは、今回の展覧会全体に大きな貢献をしていただいています。当時の美術の活動とも非常に近いところにいらっしゃって、興味深い話がうかがえるのではないかと思っています。
一柳慧さんは、作曲家、ピアニストとしてジョン・ケージなどに師事をされ、1960年代に初めてジョン・ケージを日本に紹介をするなど、非常に大きな貢献をされてきた方です。
浅田彰さんは、京都造形芸術大学大学院長、メタボリズムのメンバーのお1人である浅田孝さんがおじさまに当たります。
井口壽乃さんは、埼玉大学教養学部教授です。「空間から環境へ展」を含む当時のインターメディアな活動についてご研究されています。
最後に山口勝弘さんは、1951年の実験工房で「ヴィトリーヌ」を発表、その後も多様な芸術ジャンルと極めて近いところで活動をされてきて、日本のメディアアート界を牽引されてきた方でもあります。1968年には磯崎新さんと一緒に「環境計画」という会社を立ちあげ、一緒に万博でもさまざまなプロデュースをされています。
では、最初に井口壽乃さんから、1950年代の「実験工房」などに始まる当時のインターメディアな活動の流れを総括していただきたいと思います。
井口:私を含めて本日ここにお集まりの皆さんの多くは、「空間から環境へ展」と、これに関係する時代の芸術について、文献などを通じて知ったという方が多いと思いますので、まずは「空間から環境へ展」がどのような展覧会であったのかを大まかに振り返り、その上でこの展覧会がどのような意味を持っているのか、また美術史のなかで、どう位置づけることができるのかといった問題を、同時代の国際的な芸術動向と合わせて検討したいと考えます。
この展覧会は1966年11月11日から16日に銀座の松屋デパートの8階で開催されました。美術、デザイン、建築、写真、音楽の分野から38名が参加し、わずか6日間で35,000人の入場者があったと言われています。
もともと、この展覧会は粟津潔さんたちによるグラフィックデザインの『ペルソナ』という展覧会が企画されていたのですが、グラフィックだけではなくて、美術や音楽、建築がクロスオーバーする展覧会へと発展させたものに変わったと言われています。
展示作品全体に共通しているのは、作品の素材がアルミやプラスチックなどの新しい素材を用いていること、そしてそこに作品が置かれることによって周囲の空間が変容したり、また観客に環境を意識させるものであったり、展示方法であったりすることだと言えます。
多田美波さんの作品に見られるように、観客の姿や周囲の環境が作品に映り込み、作品そのものに観客が積極的に関与しています。この展覧会では、そうした作品が多く展示されてました。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
さて、この展覧会のタイトルに使われている「環境」という言葉ですが、これはどういう意味で使われたのでしょうか。また「環境」という言葉は、どこから来たのでしょうか。
批評家の椹木野衣さんは、1960年の世界デザイン会議で事務局長を務めた建築家・浅田孝氏にルーツがあると指摘しています。もちろん、建築界でもそのことは問題になっていたと思いますが、私は建築界から発想されたというよりも、戦後、日本の美術が、特にこの展覧会に関しては、国際的なアートシーンと同時的に展開していく中で、必然的にあらわれたキーワードであると考えます。
この展覧会に合わせて『美術手帖』は「特集=空間から環境へ」を発行し、作品の解説、国内外の現代美術の動向、特に環境を意識した作品を紹介しています。さらに磯崎新さんと東野芳明さんの対談「環境について」が掲載され、「環境芸術」の重要性が強調されています。
そして最後のページには、「エンバイラメントの会」による趣旨説明、いわゆるマニフェストともいえる宣言文が掲載されています。引用します。
われわれは、とくに新しい都市デザインや最近の美術に適応され使われ始めているENVIROMNENTという概念を意識しています。都市を建築や〈間〉の空間や機能や形態などの固定した部分の総体と考えずに、すべてが有機的に動的に関連したENVIRONMENT DESIGN。
見る者を肉体的に物質的に取り込んでしまう巨大なニューヴェルスンの彫刻やポロックの絵画の持つENVIROMNENTな性格。あるいは人間の行動を物体や偶然と衝突させ、不可知な結果を求めるハプニングな場としてのENVIROMNENT。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
ここで使われている「環境」という言葉は、イコール「都市環境」と言い変えてもいいと思いますが、都市固有の空間を意識したものであって、芸術作品においては観客にドラマのような非日常的な驚き、それまで存在していた空間の見え方が変わるようなものを「環境」という言葉で表現していたと思われます。ですから、作品には観客の参加が求められ、その意味でハプニングへと発展していくものだったと言えるでしょう。
この「空間から環境へ展」に合わせて、会期中の11月14日、草月アートセンターでハプニングが行われています。
ご存知のように草月アートセンターは1958年に開館し、1971年の閉館まで美術、音楽、演劇、ダンス、デザイン、映画の脱領域的で前衛芸術の実験の場として積極的に国内外の作家を招聘し、国際的な交流を行っていました。
1964年にはマース・カニングハムやロバート・ラウシェンバーグが公演を行いましたし、特にニューヨークでフルクサスの活動をしていたオノ・ヨーコさんが1962年に行ったハプニングは日本の現代芸術家たちに大きなインパクトを与えました。
ニューヨークに渡り、フルクサスの活動に参加した靉嘔(あい・おう)さんや、秋山邦晴さん、塩見允枝子さんが帰国し、1965年には東京のギャラリークリスタルで『フルクサスウィーク』を開催しています。靉嘔による髭を剃る、歯を磨くといった日常的な行為が舞台空間で非日常的な環境をつくり出していく、言うなれば「エンバイラメントの会」が行った彼らのハプニングは1960年代にアラン・カプローのコーネル大学のハプニングやオルデンバーグのプールのハプニングに始まり、そしてフルクサスのイベントへと発展していく、こうした世界的な現代芸術の運動体のひとつとして位置づけることができます。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
「空間から環境へ展」では、芸術領域を超えたインターメディアの傾向が見えますが、こうした脱領域的方法はその10年前の「実験工房」の活動に、そのルーツを見ることができます。よく知られるように実験工房は、批評家の瀧口修造氏と音楽家、美術家、写真家、版画家、舞台美術を手がける若い芸術家の集団で、彼らの活動はギャラリーで行われる美術展の枠を超えて、グループのメンバーがともに協働し、ひとつの空間を創造するものでした。ですから、おのずと舞台や新しいメディアを用いた活動が展開されていきます。
「バウハウス的」な舞台美術や実験的な視覚表現が生まれたのは、リーダーである瀧口修造氏がヨーロッパ流のモダニズム思想を積極的に日本に紹介し、日本に芽生えたモダンアートを育て、個々の芸術家を束ね、ひとつの運動体へと導いたからに他なりません。むろん、作品を創造した個々の芸術家の力は言うまでもありません。
その実験工房のなかでも、とりわけ新しい機械技術を積極的に芸術表現に用いようとしたのが山口勝弘さんであり、秋山邦晴さんでした。
話を1960年代に戻します。1960年代の終わりには万博を意識した展覧会が企画されるようになりますが、そのひとつが1969年4月26日から1カ月間、銀座のソニービルで開催された、「国際サイテック・アート展〈ELECTROMAGICA〉」です。これは先端技術の文化面への活用を強く意識したソニーが銀座に新しく建設した自社ビルを使った国際的なイベントで、山口勝弘さんに企画を依頼し、東レ、日本電子、IBMほか、各企業との協賛で行われたものです。
展覧会はソニービルを立体的ディスプレー装置として、アートを新しい技術と融合させ、視覚と聴覚によって、都市環境を創造する試みでした。したがって、電気、電子機器を用いた作品によってビル全体に、光、運動、音による、いわゆる環境芸術をつくり上げたのです。
こうした60年代末の展覧会には、日本国内の芸術家ばかりでなく、国外作家との交流が盛んになってきます。国際的な現代芸術のひとつの大きな流れのなかで芸術活動を展開していったその記念碑的な出来事として、また1970年の大阪万博に直接的に結びつくイベントとして、1969年2月5日から7日まで代々木体育館で開催された「クロストーク/インターメディア」というものがありました。音楽と映像とダンスによる「クロストーク/インターメディア」の印刷物にペプシコーラ社の挨拶文が書かれました。引用します。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
ペプシコーラ社は日本における現代芸術に常に深い関心を寄せてきましたが、このたび、画期的な芸術分野ともいえる「クロストーク/インターメディア」の紹介に後援できることは大変誇りとするところです。私どもは1970年に大阪で開催される万博にパビリオンを設置する計画を進めております。このパビリオンの企画は日本の最先端をゆく冒険的な芸術家たちによって練られておりますが、演じるのはパビリオンを訪れる人たちなんです。パビリオンの中での来訪者の動きが光と音の織りなす一大環境芸術をつくり出す仕組みです。どうぞご期待ください。
このイベントは、実験工房のメンバーの湯浅譲二さんと秋山邦晴さんとロジャー・レイノルズの企画で、アメリカ文化センターのオルブライト氏が主催して、アメリカ大使館ほか、パン・アメリカン航空、ロックフェラー財団、日本の企業が協力しています。つまりこれはアメリカがその翌年の大阪万博に出品するための予行練習のようなものでした。
出演者は、音楽では、武満徹さん、湯浅譲二さん、秋山邦晴さんと一柳慧さん、そしてフルクサスのメンバーの小杉武久さんと塩見允枝子さん、アメリカからジョン・ケージ、マース・カニングハム・カンパニー、こちらは音楽担当のゴードン・ムンマ、ロバート・アシュレイ、アルヴィン・ルシエ、そしてロジャー・レイノルズが加わっていました。映像では飯村隆彦さん、松本俊夫さん、エクスパンデッド・シネマのスタン・ヴァンダービークさん、ロナルド・メナス、舞台デザインを山口勝弘さんと今井直次さんが担当し、土方巽さんが舞踏を披露しました。

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
音と映像と光のメディアが混然となった21作品が3日間上映され、毎晩3,000人を超える聴衆が会場を占める盛況ぶりだったと言われています。会場の巨大な円形ドームの空間に特別に設置された14チャンネルの音と映像の移動装置によって、観客はディスコティークのような空間で、これまでの芸術鑑賞とは異なる体験をする、当然ながら、今スライドで映していますが、1966年秋の、ニューヨークでEATが開催した「九つの夕べ――演劇とエンジニアリング」を意識しており、EATの「九つの夕べ」をしのぐ内容と規模を目指していたと考えられます。
大阪万博のペプシ館はアメリカのエンジニアリング、先ほど申し上げたEATのビリー・クリューヴァー氏とラウシェンーグが中心となっていたことは、よく知られています。こうした日本とアメリカ、相互の交流を可能にしたのは、日本人メンバーの中谷芙二子さんが重要な役割を果たしていました。
パビリオンの内部にはミラードームによって映像のディストーション効果を演出しているということ、そして中谷さんの「霧の彫刻」が示したように、屋外に新しい環境をつくり出す、つまりギャラリーのような閉じられた空間ではなく、屋外の開かれた空間で環境芸術の整合を見たのです。その意味では「空間から環境へ展」から、このペプシコーラ館に見るような万博へつながるストーリーが描ける。60年代の環境芸術が、1970年の大阪万博で集大成されるというストーリーを描けると思います。
以上、「空間から環境へ展」を中心に1950年代から60年代の日本の芸術界振り返りますと、20世紀初頭のバウハウスをはじめヨーロッパのモダニストたちのアイディアを発展させながら、日本の芸術家たちが同時代の世界の芸術運動に呼応しながら発展させてきた、そうした結果であったのだと私は考えています。
<関連リンク>
・シンポジウム「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」
第1回 「空間から環境へ展」とは
第2回 日常の意識を拡張する
第3回 建築、都市デザイン、政治から見た「環境」
第4回 大阪万博:テクノロジーと芸術の融合を試みた環境
第5回 新しい時代に向けたヴィジョンとしての環境
・「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」
会期:2011年9月17日(土)~2012年1月15日(日)