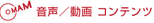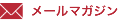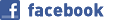1960年代~70年代のメタボリズムの全盛期には、建築や都市計画の分野だけでなく、美術や音楽などジャンルを超えた横断的な活動や交流が活発に行われました。建築が単体の建物から都市のインフラなども包括したメガストラクチャーへと拡張するなか、美術の分野でも表現のための空間は、「環境」あるいは「エンバイロメント」という言葉に置き換えられ、大きく拡張しました。2011年12月18日(日)に開催された「メタボリズムの未来都市展」第5回シンポジウムでは、「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」というテーマで、当時渦中にいた建築家、アーティスト、作曲家、あるいはその時代の研究者や批評家を招き、活発な議論が展開されました。その模様を連載でお伝えします。
連載(3)では、メタボリズムの建築家のなかでも、当時の前衛芸術運動やインターメディアな活動と最も深く関与していた磯崎新氏が、「環境」について解説します。ヨーロッパのアヴァンギャルド、モダンデザイン、モダン建築の文脈における「空間、時間、建築」の概念と、その近代の概念を超えたところに求められた「環境」の概念、さらには第二次大戦前・戦中の大東亜共栄圏という政治的文脈から見た「外部としての環境」、そして戦後、日本的な空間観念が求められたところからみる「環境」など、極めて多角的な視点から整理されています。
メタボリズムの未来都市 関連シンポジウム第5回「空間から環境へ」
2011年12月18日
[出演: 浅田 彰(京都造形芸術大学大学院長)、井口壽乃(埼玉大学教授)、磯崎 新(建築家)、一柳 慧(作曲家、ピアニスト)、山口勝弘(美術家) モデレーター: 片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター)]

建築家 磯崎 新さん
撮影:御厨慎一郎
片岡:続いて、磯崎さんにお話をいただきたいと思います。建築家の立場から、当時の美術家、もしくは音楽家とも交流されていた磯崎さんですが、「環境」という用語について、建築の世界では1940年ごろからすでに注目はされていたということですよね。建築の側から見た「環境」もしくは「エンバイロメント」についてお話しいただけますか。
磯崎:先ほどからのお話に全部引っかけてしゃべるのはちょっと難しいのですが、できるだけつないで話ができたらと思っています。
「空間から環境へ展」の趣旨にある一文、「新しい都市デザインや最近の美術に適応され始めているENVIRONMENTという概念を意識しています」という説明が、いわば一種のマニフェストに近いようなものです。
ここで僕はどちらかといえば、「じゃあ都市デザインというものが、一体環境とどういうかかわりを持ったのか」、これは今回の展覧会のメタボリズムといろいろつながっている問題のひとつですが、この点についてご説明をしたいと思います。
山口さんがキースラーの話をされました。ヨーロッパのアヴァンギャルド、いわゆるモダンデザイン、モダン建築、主としてバウハウスですね。バウハウスを中心になって動いていた、この動きとは、キースラーは少し、一歩距離をとってアヴァンギャルドでやってきたアーティスト兼彫刻家、建築家だったと僕は思うのです。1930年ごろからドイツの状況が非常に変わってきますので、1920年代に積み上げた新しい動きを、さまざまな形でアメリカに持って流れていった人たちがたくさんいます。
そのうちのひとつのグループが先ほどお話に出たブラック・マウンテン、そこで教えていたりしたような人たちです。大体、みんなバウハウスの流れの人が多いわけです。
同時に、1930年ごろ、日本にもこの流れは入ってきた。日本ではどちらかというとコルビュジエで、コルビュジエはバウハウスとは並行しているけれど関係はないのですが、CIAMという20年代の末にでき上がった建築運動の中ではバウハウスのグループ、それからコルビュジエたちのグループ、こういう大きな二つの流れがみんな一緒になって動き始めました。ここで学んだ人たちが日本に戻ってきて近代建築の流れを日本の中で考え始めた。つまり20年代のものを、30年代を通じてアメリカと日本両方に持ってきたというように考えてもいいと思います。ですから、日本がモダニズムというか、バウハウスを受け取り始めたのは、アメリカと全く同じ時期だったと考えてもらっていいと思うのです。

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
アメリカの中で、実はこの運動の中心になっていた人たちのなかに、CIAMのいわば書記長、ジェネラルセクレタリーをやっていたギーディオンという美術批評家がいます。ギーディオンはハーバードで40年前後に講義をしますが、それが本になって出てきたのが、『Space, Time and Architecture』、日本で『空間・時間・建築』と訳されている本です。この本が、言うならばモダニズムのデザイン、建築、それにすべてモダンアートの流れもかかわっている。こういう説明がきちんとまとまって出た、恐らくテキストの一番中心になるような本だったと僕らは学生のときに思いました。僕が学生のときは50年以降ですが、そのころにこの英語の本がやっと日本に到達して、まだ訳されていないのですが、最大のテキストだったというように記憶しています。
このときに、TimeとSpaceとArchitectureという三つの言葉がタイトルになっていた。この三つが考えられれば、モダンデザイン、現在建築も美術もデザインも全部理屈が通る。これくらい明快な全体の組織、これは建築から都市に至るまで、すべての流れを説明してあります。
その流れの中から、ハーバードで50年代の終わりごろにGSDと今呼ばれているアーバンデザインという言葉が初めて登場する学科ができます。これが、ギーディオンたちの考えがひとつインスティテューショナライズされてできた学科であり、こういうひとつの大きな流れのなかにあった。
日本でメタボリズムというものが議論をされ始めたときが、ちょうどこのGSD、ハーバードのアーバンデザイン学科ができ上がったのと同時期であったことを、頭に置いていただけるといいと思います。
一体近代建築というもの、近代デザインというものを、時間と空間と建築で、どのようにギーディオンが説明してきたかが、この本、あるいは、この美術の流れの一番大きい点です。
もともとウィーンの人で、ウィーンで学び、美術の様式論を確立したといわれるヴェルフリンの系統で、きちんとその次の理論をつくるべき立場にいた人ですが、近代デザインの運動が起こったときにスカウトされて、その書記長になったわけです。だからいろいろな段取りや理論化というものは、全部彼がやった。彼がハーバードに行ったということが、ヨーロッパでの大きな流れのひとつだと思います。もうひとつの流れとして、バウハウス系統のヒルベルザイマーやミースがシカゴに行き、これがニュー・バウハウスになった。この二つがアメリカに行ったのです。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
一方で、日本ではコルビュジエを学んだ人たちが建築などを始めたというように言っていいと思います。その中にはタウトから始まる日本の古いものの解釈も入ってきます。
これは勝手な意見で、決して承認されている考えではないのですが、1950年という時期を仮にとってみると、日本は占領下にありました。占領軍としてのアメリカが日本から何かを持っていった、戦利品として何かを持っていったということがあるのですが、考えてみたら、持っていくものがなかったわけです。
このときにデザインや建築の世界でジャポニカと呼ばれていたひとつの流れがあります。これはどういう流れかというと、モダニズムの視点で日本を見ることのできたイサム・ノグチ、石元泰博、こういう人たちが解釈した日本。もちろんドイツ語でタウトの本が出ておりましたけれど、日本をそういう形で解釈した人が、ひとつの美学を発見した、組み立てた。この美学がジャポニカと言われて、日本では「フジヤマ・ゲイシャと同格だ、浴衣、扇子と草履というようなものだよ」と言われていましたが、実はそうではなくて、もう少しこういう人たちのデザインの解釈があったのです。
僕の考えはちょっといい加減ですが、アメリカが受け取ったシカゴ派、それからギーディオンもそうですが、ギーディオンがヨーロッパのものをアメリカに持って行った。シカゴではアメリカのそういう立場、バウハウスの思考をアメリカのテクノロジーを結びつけて展開していった。ですから、非常にテクノロジーの流れの中でのデザインができた。だけれど、そこには美学がなかったのではないか。その美学を補完するためにジャポニカが戦利品として日本から持って行かれたのではないか。これが1950年代の半ばごろのアメリカの日本ブーム、日本デザインブームというものの一環であると見ていいのではないかと思うのです。
それをいろいろ考えてみると、日本でそれに当たる、つまりアメリカに持っていけるような日本の美学がいつでき上がったかというと、これもまた1930年ごろにコルビュジエを学んで帰ってきた日本の建築家たちが、日本の古典を解釈しながらつくり上げてきた日本的な発想というか思考、これが一方にあった。
そのときに何があったかというと、ギーディオンの思想をずっとみんな勉強したのですが、日本で「時間、空間、建築だけでは、ヨーロッパと同じじゃないか、むしろ日本独自のものがそこにあるのではないか」ということが、戦争中に盛んに議論された。この一番中心になった人は、最終的には浜口隆一さんという丹下健三さんの同級生の批評家で、前川さんのところで学んだ人です。浜口が考え始めたものは、要するに「空間を超えるものとして、『環境』という言葉が出てくるのではないか」ということで、すでにそのとき、そのようなことが言われています。先ほど浅田さんのお話に出た、おじさんの浅田孝さんは、ちょうど、そのころ大学を卒業した方ですから、一緒に理論を組み立てていく中にいた人です。

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
日本の問題は、八紘一宇とか大東亜共栄圏という形で外に進出してしまったのです。そうすると、それまで「日本」というように考えてきた、「日本的だ」というように考えられていた、この美学にしても、思考の形式にしても、これがバンコクでうまく使えないといけない、これが満州で使えないといけない、支那の奥地でこれを議論するとしたらどうなるか。つまりひとつの思考の形式の中で、閉ざされたひとつの空間だと思っていたものが、外に出て行ったら、そのままのことが使えない。これをどうするかというのが、建築家、前川さん、丹下さんたちの1942、3年ごろの一番の問題点だったというように思います。
タイのコンペをやったときの説明文に、前川さんは「環境的空間」というのを使い始めた。それから、丹下さんは、それに対して、「都市計画を先にやって、都市という外側の環境を受け取ることによってデザインをつくり始める」という言い方をし始めました。つまり、建築の思想の中に外部が意識され始めた。「この外部が環境だったのだ」というのが、僕が感じるところです。
そういうことは戦後になってもずっとつながっていって、その中から出てきた日本的な美学みたいなもの、これがアメリカにもつながっていったと思うのです。ちょうど僕はそのころ学生になったのですが、先生たちは、「実は環境という言葉はあまり言いたくない」と使いませんでした。その理由は、戦争中の思い出があるためです。大東亜共栄圏のためにこういう理論をつくっていたということを口に出すわけにいかない政治情勢にあり、口を閉ざしていたという状況です。「メタボリズムの未来都市展」の第1室にあるものをいろいろな角度で解釈すると、そのときに建築家がいかに苦労したかということがわかると思います。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
こういう状態があった上で、そのなかから、もうひとつ環境というものを言う必要があるのではないか。それはどういうことかというと、近代建築のTime, Space, Architectureという、この抽象化した近代の議論をもうひとつ超えるには、やはり環境ではないかという形の議論が、たまたまハーバードのデザイン学科GSDでも生まれ初めてきた。
そして、それがいろいろな意味で、日本の歴史的なもの、近代デザインが一緒に混じってでき上がってきた。そのときに一番デザイン上、問題となったのは、単なる時間、単なる空間ではなくて、時間というのは、先ほどのケージの話に出たように、瞬間はmomentと解釈すべきではないか。それから、時間というものはoccasion、空間というのはenvironmentというように解釈するのがいいのではないかというふうに、だんだん議論が移っていった。これが、つまり都市デザイン側、建築デザイン側の、このエンバイロメントというものが頭にあって出てきたところのひとつのきっかけだったと僕は思います。
それぞれのアーティストが、これをどう理解して、どう解釈したか、何をやったかというのは、そこからあとの問題なのです。
<関連リンク>
・シンポジウム「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」
第1回 「空間から環境へ展」とは
第2回 日常の意識を拡張する
第3回 建築、都市デザイン、政治から見た「環境」
第4回 大阪万博:テクノロジーと芸術の融合を試みた環境
第5回 新しい時代に向けたヴィジョンとしての環境
・「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」
会期:2011年9月17日(土)~2012年1月15日(日)