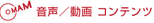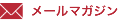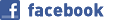1960年代~70年代のメタボリズムの全盛期には、建築や都市計画の分野だけでなく、美術や音楽などジャンルを超えた横断的な活動や交流が活発に行われました。建築が単体の建物から都市のインフラなども包括したメガストラクチャーへと拡張するなか、美術の分野でも表現のための空間は、「環境」あるいは「エンバイロメント」という言葉に置き換えられ、大きく拡張しました。2011年12月18日(日)に開催された「メタボリズムの未来都市展」第5回シンポジウムでは、「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」というテーマで、当時渦中にいた建築家、アーティスト、作曲家、あるいはその時代の研究者や批評家を招き、活発な議論が展開されました。その模様を連載でお伝えします。
連載の最後となる(5)は、浅田氏から磯崎氏への質問から始まります。コンピュータライズされてイメージが錯綜し、芸術の諸領域も融合する空間を「サイバネティック・エンバイロメント」と呼んだこと、そこから派生して井口氏からは60年代のアートシーンを考える際には社会的、政治的な背景も併せて検証する必要があるとの指摘、さらに一柳氏からはテクノロジーを採用した電子音楽のパフォーマンス化、ライブ化の背景など、話題は多岐に亘ります。
テクノロジー自体は半世紀後の現在とは比較にならないものだったはずですが、芸術の諸領域それぞれから新しい時代に向けたヴィジョンが生まれ、それらを融合させる実験の場としてあったのが万博であり、その前哨戦としての「空間から環境へ展」であったように思います。技術的には当時のさまざまな夢が実現可能な現在、私たちはまたどのような「環境」を描いていけば良いのでしょうか。示唆に溢れる議論であったと思います。登壇者のみなさま、改めて有り難うございました。
メタボリズムの未来都市 関連シンポジウム第5回「空間から環境へ」
2011年12月18日
[出演: 浅田 彰(京都造形芸術大学大学院長)、井口壽乃(埼玉大学教授)、磯崎 新(建築家)、一柳 慧(作曲家、ピアニスト)、山口勝弘(美術家) モデレーター: 片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター)]

浅田 彰さん
撮影:御厨慎一郎
浅田:磯崎さんに二つだけ質問をしていいですか。
まず、磯崎さんは「サイバネティック・エンバイロメント」の議論なども含む『建築の解体』でそれまでの近代建築とは違う方向を打ち出されるわけですが、その前の、最初の本は確か『空間へ』というタイトルですね。そのときから、「空間」というのは、ギーディオンが言っていたような近代主義的な空間とはすでに違うとらえ方だったと思うのですが、あそこで「環境」ではなく「空間」だったのはなぜかというのが第一の質問です。
それから、磯崎さんは一方では丹下健三門下で、まさに建築・都市計画の主流にいながら、他方では、当時の建築家としては例外的に前衛芸術の最前線と深くかかわっておられた。そのことと、ギーディオン的な時間や空間を組み替えていく上で磯崎さんが最もラディカルなところまでいっておられたことは、密接に結びついていると思うんです。例えば、メタボリズムは生物モデルに従って成長や変化を重視するけれど、所詮は有機的全体性(ひとつの幹から枝葉が分かれるというような)を前提としており、クリストファー・アレクサンダーの「都市はツリーではない」の批判の射程内に入ってしまうのだけれど、磯崎さんは「孵化過程」で観客参加型の都市計画のシミュレーションをすることで別の角度からメタボリズムを根源的に相対化してみせた。また、メタボリズムは変化とか成長とか言うとき未来に向かうリニアな時間を前提としているけれど、磯崎さんはその未来の行き着いた先に再び廃墟が回帰するという循環的な時間を考えていて、それを「電気的迷宮」の「再び廃墟になったヒロシマ」のようなコラージュで示してみせた。その意味で、たとえば黒川紀章さんは磯崎さんより年齢は下ですが、黒川さんが典型的なメタボリストだとすれば、磯崎さんは最初からポストメタボリストと言うべき存在だったと思うんです。このように、磯崎さんが特権的にアートと非常に近いところで建築や都市デザインを考えておられたということが、メタボリズムとのある種の距離を生んでいると思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。
磯崎:最初のほうの、なぜ『空間へ』とつけたかというのは、これはもう全く僕自身が半分、責任があるのか、ないのか。つまり、『環境へ』などというタイトルで出しても本は売れないだろうと(笑)。単純にそういうことで、これでコルビュジエが『建築へ』というので、やっとみんな考え始めた時期だから、『空間へ』にしておけと。
「建築の時間論をやりたかった」というのが60年代の僕のすべてで、自分で書いた文章は、ですからプロセスとか、こういうような概念のほうを自分ではより重視しているのですが、それじゃあ売れないというのがあるので、こういうタイトルは、常に適当にやったというようなところです(笑)。
極端に言うと、「環境」というのは1940年から引きずっているコンセプトです。でも、当然ながら近代建築というのは20年代のコンセプトにすぎないというように我々は思っている。
じゃあ、その先をどうしたらいいのかというのが、恐らく僕にとってみると60年代に自分で考え始めたときのひとつの、ひそかな試みをやりたいと思いながら、結果的に建築家というのは、やれるものしかできない、やれる範囲でしかできないということだったわけです。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
一番そのときに考えてきたことは、その当時、「サイバネティック・エンバイロメント」という、これも流行りの言葉ですね。サイバネティックスというウィーナーの言葉を使って、コンピュータライズして、電脳的で、電脳がなかったので電気的という、そういう空間にいろいろなイメージが錯綜するようなもの。これは「都市そのものもそうだ」ということから、「サイバネティック・エンバイロメント」という呼び方をしました。それでこの動きの中に、都市のコンセプト、デザインのコンセプト、アートも音楽も、さまざまなものがすべてごったに入っていく、そういうイメージを実現できないかと考えたのです。
つまりテクノロジーがあるとは言っても、僕自身、それに追いつかないわけですね。それでたまたまお祭り広場でロボットの設計をやりましたが、ロボットというのは、今だったら日本に最高の技術がありますが、当時ないわけです。何をやったかというと、「動くものをつくれるとしたら、電車の車両をつくる会社だから車両屋に頼もう」と台車をつくるとか、「建設機械屋さんに、じゃあアームをつくってもらおう」とか、こういうレベルで組み立てたハイブリッドですけれど。まあ、ともかく性能が悪いわけです。それで、しょうがないので、木偶の坊からとって、「デク」ロボットという名前をつけたというのがいきさつです。
こういういい加減なことをやりながら、テクノロジーというものを、何とかしていろいろな思考のひとつの流れに据えたいと思っていたというぐらいです。僕にとってみると、ある意味での万博のやれた範囲というものは、そのくらいまでだったのです。
現実に、山口さんのやったパビリオンであるとか、一柳さんは、このお祭り広場にもかかわっていただきましたが、さまざまなところで、一柳さんは音楽をそういう中で組み立てられていた。そして、そのなかから環境音楽じゃなくて、何だっけ、一柳さんの音楽、今でいうウォークマンのはしりみたいなものをつくっておられたじゃない?そういうものを一柳さんはつくって、音楽が至るところに散らばって出現する、そういうようなものが出てきます。
山口さんは当然ながら、そういうもののプロデュースを実際にはたくさんされたわけですけれども、このなかでは、つまり、どちらかといえば、「純粋アートと見えないようにしたい」というのが、一番の共通のイメージだったのかもしれません。

井口壽乃さん
撮影:御厨慎一郎
井口:今「サイバネティックス」という言葉が出たので少し補足すると、これを芸術のことばとして使ったのは、ニコラ・シェフェールというハンガリー出身のユダヤ人です。1970年代、日本でも彼の本が翻訳出版されています。自然環境、つまり風や光や、空気の流れだとか、情報ということをトータルに造形芸術、彫刻の中に取り入れて、それを自動制御していくということを言ったのです。
60年代の話を今、磯崎さんが建築の立場からお話ししていましたが、ここにデザイナーの方がいらっしゃらないので、デザインの側から発言させていただきます。
「空間から環境へ展」のなかで、例えばグラフィックデザイナーの勝井三雄さんの作品はプラスチックのキューブの立体物にシルクスクリーンで抽象的な模様を印刷して、それを天井からつるすというものでした。
グラフィックデザイナーたちが、60年代にどんな仕事を展開していくかというと、ひとつつの例としてわかりやすいのは、ハーバート・バイヤー、バウハウスからアメリカに渡ったバイヤーです。バイヤーは1960年にキーノートスピーカーとして、世界デザイン会議WoDeCoに招聘されて来日します。、バイヤーは、コロラド州アスペンというところで、庭をつくったり、公園をつくったりとか、壁画をつくったり、グラフィックデザインから離れて、環境アート、パブリックアートへと展開していきます。
これをサポートしたのは、シカゴのコンテナー・コーポレーション・オブ・アメリカ、CCA、コンテナの会社のウオルター・ペプケという事業家です。段ボール箱を売る会社ですが、そのペプケがヨーロッパから亡命してきたアーティスト、ケペシュたちに会社の仕事としてデザインをさせています。MITにいったケペシュは、1940年代戦時下で戦争プロパガンダとしてかかわっていくのです。
アメリカとの関係でオルブライト氏の話をしましたけれど、なぜ戦後の日本のアーティストたちがニューヨークに渡ったか、またアメリカとこんなに結びつきがあったのか、ということに注目しなければいけないと思います。
1945年、終戦後、GHQのなかに、日本の民間人、一般国民に対して教育をしていく指導的中枢であった民間情報教育局というのがありました。CIEと呼ばれています。Civil Information & Education Section。戦後日本を軍事占領した連合国司令官の組織の中の情報部、その下部組織としてありました。それが、東京の旧NHKの108号室に1945年11月に図書館をつくり英語の書物をたくさん置いた。モホリ=ナジの『ビジョン・インモーション』や、ケペシュの『ランゲッジ・オブ・ビジョン』など、アートに関する英語の本があった。以前、山口さんが「それをよく読んでいた」とおっしゃったことがあり、秋山さんも、そこに通ってよく読んでいたそうです。EATの活動をサポートしていたのが、そのCIEのアメリカ文化センターです。アメリカ文化センターという名前にあとで変わったのです。
私が言いたいのは、60年代のアートシーンを考えていくとき、美術史の文脈だけでは解釈できなくて、経済と産業界と、そして芸術家のかかわりということ、そしてその背後に、日本とアメリカとの関係という問題が非常に重層的にかかわってくるということを、もうちょっと分析、検証しなければいけないのではないかと感じています。
このあたりのご専門は浅田さん?
浅田:専門ではありませんが、そのとおりだと思います。
片岡:「メタボリズムの未来都市展」の展示の中「空間から環境へ」のセクションで、一柳さんが作曲された《生活空間のための音楽》を流しています。それは当時使える最先端の技術を駆使して、黒川さんの建築論をコンピュータが肉声を模倣して話しているというものです。
それから、半世紀たって、テクノロジーによって可能になったことは随分あるのではないかと思うのです。また逆に、アナログであるがゆえに可能な表現というのも続いているように思うのですが。一柳さん、この辺りについてのお考えを教えていただけますでしょうか?

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
一柳:先ほど磯崎さんが「エレクトリック・ラビリンス」の話をされて、すばらしい作品だったので、私もお手伝いさせていただきました。ああいうときに一番困るのは、音楽ではインスタレーションというのが非常にやりにくいということです。特に音楽はパフォーミングアートですから、普通、皆さんも音楽会に行かれると、せいぜい2時間ぐらい、長いオペラでも3時間ぐらいでパフォーマンスが終わってしまう。万博などのように半年間続くものに音楽をどういう形で入れ込むかというのは、音楽家にとっては非常に大きな課題で、それに耐え得るテクノロジーが背景にないとやはりできない。
その点ではいろいろ磯崎さんからも学ばせていただいたのですが、電子音楽スタジオというのができたのが1952年で、これはシュトックハウゼンとシュトックハウゼンの先生であったアイメルトの2人がケルンにつくったものです。
しかし、ジョン・ケージは1930年代からすでに電子音を使っているのです。特に発振機による電子音を使っていて、彼の作品で「イマージナリー・ランドスケープ」というのがあるのですが、この中でもう1930年代に使っています。
ドイツで電子音楽ができたのが1952年、その4年ほど前にフランスのピエール・シェフェールが「ミュージック・コンプレート」というのを1948年につくっていますが、これは電子音楽ではなくて、環境の中のいろいろな声をレコードのターンテーブルを利用してつくったわけです。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
ただ、シェフェールの場合も、シュトックハウゼンの場合もそうですが、これをいずれもスタジオの中で電子機器を用いて、そこに何人かのエンジニアが作曲家に協力して作品をつくるという形のものです。
ところが、日本はできたのがもうちょっとあとですけれども、アメリカでは、例えばプリンストン大学、コロンビア大学、イエールとか、いろいろなところに電子音楽スタジオができ、アメリカの作曲家が呼ばれて、そこで製作をするということが行われていました。
アメリカには三つ音楽界があって、ひとつは日本でいうところの楽団と呼ばれるような音楽学校とかオーケストラとかオペラ団体など、それに当たるのがひとつ。もうひとつは、大学附属の音楽部というもの。これが活動としては一番活発なのですが、それが戦後はいろいろあった音楽学校を吸収して、全部大学附属の音楽部にしていくということがあった。三つ目はフリーランスでやっている人たちです。
ジョン・ケージなんかは、もちろん、完全にフリーランスでやっていた人です。電子音楽とかコンピュータとか新しいものにも非常に関心があったし、今まで聞こえなかった音をコンタクトマイクなんか使って聞き出そうとしたり、いろいろやっていた人で、できるだけ、そういう機械を利用するところに近づきたいと思って働きかけたのですね。ところが、残念なことに、アメリカもそういうところは相当なもので、今申し上げたような有名大学は全部拒絶したのです。「ケージのような人はやらなくていい」ということなのでしょうね。
そこで終わらなかったのがおもしろかったのですけれども、ケージはケージなりに考えて、ちょうど楽器を演奏するのと同じように舞台に機材を持ち込んで、舞台で生の演奏をする、スタジオにこもって作曲するこれまでのシュトックハウゼン流の電子音楽ではなくて、生の演奏を舞台上で展開するということをやり始めたのです。
これが一番インターメディアなど、今もそうですけれど、のちのちの本流につながっている。つまり先ほど言いました、今やインスタレーションなどもそういう形で、いろいろな機材を使って比較的簡単にできるようになりました。そういうのは、全部ケージのライブ・パフォーマンスといっていますけれども、ライブ・エレクトロニック・パフォーマンスや、ライブ・コンピュータ・パフォーマンスなどは、スタジオで電子音楽製作を拒絶されたがゆえに、逆に非常に生々しく出てきて、パフォーマンスと一体になったということです。これが、シュトックハウゼンの時代から見ると、その後の電子音楽、コンピュータ音楽の方向性をグッと変えたということも、ここにひとつあるのですね。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
もうひとつは、音楽にも企業秘密というのがありますんで、それを全部ばらすわけにもいかない。この中には多分音楽家の方はあまりいらっしゃらないと思いますけれども。
つまり音楽のほうは逆に「時間芸術」とヨーロッパでは定義されてきましたけれども、19世紀の後半ぐらいから、時間の要素がどんどんなくなってくるわけです。例えば、ワーグナーなどの無限旋律などをつくっていますけれど、無限旋律のようにだんだん、だんだん、いろいろ旋律が長く続いたり、それからシェーンベルクのような人たちになってくると、ひとつひとつの音を大事にするがゆえに、ひとつひとつの音では時間がなかなか有機的に結びつけられないというようなことも出てきたりして、時間の要素がどんどん減ってきた。もし歴史的にまとめると、さっきのケージの『4分33秒』が、時間がゼロになった地点です。ところが時間がなくなってきただけでは音楽というのはどんどん成立しにくくなってくるものですから、私は、音楽に建築家や美術の方々たちが、いつも考えておられる「空間性」というものをできれば導入して、それで音楽の時間が欠落してきたこと相互に補ったり、あるいは相互浸透させたりしながらやっていけないかなと思ってやってきました。その先に、さっきから出ている「環境」の問題というのが、音楽と結びついて出てきた。さっき磯崎さんがちょっと言われて、ちゃんとお返事できなかったのですが、私がやったのは音響デザインといいますかね。
デザイナーというのが、特に日本で出てきたのが、60年代ぐらいが最初といっていいですね。アーティストたちはその辺は非常にナイーブで、なかなか社会とか経済とかと結びつかないところで、自分なりの仕事をしておりましたけれど、デザイナーはどんどん社会に出て行って、要するに広告界や経済界との仕事が非常に多くなってきた。
そういう関係からも、音楽を音楽の中に閉じ込めないで、日常性に開放することで、環境デザインというものも片方では考えられないかなということでやってきた。そのちょうど途中ぐらいで、大阪万博とかの音楽にそれが結びついてきたというのが現状です。

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
浅田:今の一柳さんのお話はとてもおもしろかったので、くだらないことをひとつだけつけ加えます。ジョン・ケージという人は歴史的に非常に意味深い位置にいるんですね。1933年にナチスが政権をとって、シェーンベルクは亡命を余儀なくされる。結果、ドイツ・オーストリア音楽を最先端で受け継いだシェーンベルクのような人が、こともあろうにアメリカ西海岸で教えることになる。その弟子のひとりがケージだった。しかし、ケージはそこから逸脱しさっきおっしゃったように、東洋、とくに日本の禅の影響を受けとって変わっていくわけですよね。
その手前で、西海岸でシェーンベルクに学んだあと、ニューヨークにたどりつき、ペギー・グッゲンハイムとマックス・エルンストの家に転がり込んで、デュシャンなどと出会い、そっちのほうに引っ張られていくというような経緯があったのですが、途中でシカゴに寄ったら、モホイ=ナジがまさにニュー・バウハウスの後継のデザイン学校をやっていて、そこで音楽を教えることになり、音響スタジオのようなものをつくることも考える、しかし、その計画はうまくいかず、結局そこは短期間で離れることになるんです。それも含めて、一柳さんが言われたように、アカデミックな場所にスタジオみたいな根拠地を持てなかったことが、逆にパフォーマンスの現場でのライブ・エレクトロニクスの実験につながった。とても面白い話ですね。
ちなみに、ピアニストとして活躍しながら、まさにそこで電子音楽の世界に入って行ったディヴィッド・チュードアが、EATのメンバーとして大阪万博ペプシ館にも参加しており、そのときの音響が中谷芙二子・高谷史郎の作品によってよみがえったりもしている。このように、40年前はテクノロジーの限界があって実現できなかった夢が、いま少しずつ実現されつつある。言い換えれば、やっと時代が当時のアーティストたちの構想力に追いついてきたのかもしれません。
片岡:ありがとうございました。非常に中身の濃い話で、まだまだ本当はあと何時間も続けられそうですけれども、残念ながらこのあたりで時間となりましたので終了させていただきたいと思います。登壇者の皆様、どうもありがとうございました。

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
<関連リンク>
・シンポジウム「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」
第1回 「空間から環境へ展」とは
第2回 日常の意識を拡張する
第3回 建築、都市デザイン、政治から見た「環境」
第4回 大阪万博:テクノロジーと芸術の融合を試みた環境
第5回 新しい時代に向けたヴィジョンとしての環境
・「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」
会期:2011年9月17日(土)~2012年1月15日(日)