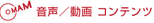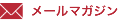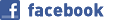1960年代~70年代のメタボリズムの全盛期には、建築や都市計画の分野だけでなく、美術や音楽などジャンルを超えた横断的な活動や交流が活発に行われました。建築が単体の建物から都市のインフラなども包括したメガストラクチャーへと拡張するなか、美術の分野でも表現のための空間は、「環境」あるいは「エンバイロメント」という言葉に置き換えられ、大きく拡張しました。2011年12月18日(日)に開催された「メタボリズムの未来都市展」第5回シンポジウムでは、「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」というテーマで、当時渦中にいた建築家、アーティスト、作曲家、あるいはその時代の研究者や批評家を招き、活発な議論が展開されました。その模様を連載でお伝えします。
連載(4)では、いよいよ万博の話題に移行します。三井グループ館の総合プロデュースをした山口氏から資料が配布されたあと、浅田氏が万博の主要パビリオンにおける、当時の限定的なテクノロジーとアートとのクリエイティブな融合について紹介します。続いて磯崎氏からは、戦後のヨーロッパ、アメリカ、そして日本の建築やデザインの動向や文脈を多角的に読み解きながら、万博や自身のインスタレーション作品を通して、建築、アート、音楽、デザイン、写真といった芸術の諸領域、あるいはクリエイターと観客の境界なども無化させた、現在で言えば「参加型」の表現から生まれる「環境」についての発言が続きます。
メタボリズムの未来都市 関連シンポジウム第5回「空間から環境へ」
2011年12月18日
[出演: 浅田 彰(京都造形芸術大学大学院長)、井口壽乃(埼玉大学教授)、磯崎 新(建築家)、一柳 慧(作曲家、ピアニスト)、山口勝弘(美術家) モデレーター: 片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター)]

山口勝弘さん
撮影:御厨慎一郎
片岡:本日、大阪万博での三井テーマ館の資料を配布させていただきました。大阪万博で山口さんが総合プロデューサーをされて、そのサウンドを一柳さんがされたものですが、山口さん、資料の説明をしていただいてもよろしいでしょうか。
山口:大阪で万国博が開かれたときに、僕は三井グループ館の設計、あるいは計画全部を東隆光さんという建築家、倉俣史朗というインテリアデザイナーをやっていた人、それから伊原道夫という造形作家、この人たちと相談しながら、音楽は一柳さんと実験工房の佐藤圭次郎にお願いしました。
佐藤圭次郎さんは作曲家でありながら、やがてオブジェをつくったりして、非常に自由に行動していた人です。この佐藤圭次郎さんの大展覧会が多摩美術大学の美術館で来年開かれる予定になっています。
僕は来年開かれる「実験工房回顧展」にも関係しようと思っているのです。というのは、実験工房というのは、1950年代の初めに東京で立ちあがったグループ活動で、この「実験工房回顧展」のときに、実験工房について一度みんなで話す、こういうシンポジウムをやろうと今考えております。ですから、万博のことも含めて細かい話は、そのとき話をすればいいんじゃないかと思います。
片岡:わかりました。ありがとうございます。それでは続いて、浅田彰さん、これまでのところについて当時の日本の社会的背景も踏まえてご意見いただけますか。
浅田:僕は浅田孝の甥ということで呼んでいただいたわけですが、僕が叔父を代弁することはできません。そもそもクリエイターが亡くなったあと遺族が出てきていろいろ言い出すので困ることが多い、そういうことはしたくないんですね。その上で言えば、僕は父親世代にエディプス的な敵対意識をとくに持たなかったし、浅田孝はいつも面白い話をするので興味深く聞いていたけれど、1957年生まれのガキとしてはやはり高度経済成長を支えた父親世代のイデオロギーに違和感をもっていた。大阪万博のときは13歳で、名前くらいは知り始めた前衛芸術のスターたちが来ているらしいというので興味はもったものの、そもそも国民的祭典と称する盛り上がりが耐え難く、一度だけ見に行ったけれど行列に辟易してすぐ逃げ出したというのが万博体験のすべてです。実際、当時は国家と資本の祭典に前衛芸術家が協力するのを批判する反対派もずいぶん多かったんですね。しかし、別の角度から見直せば、国家と資本の祭典にあれほど多くの前衛芸術家が招聘されたのは空前絶後のことで、実際そこでは非常に面白い実験も行なわれていた。この場では、叔父とは別の一個人として、メタボリズムから大阪万博にいたる時代について、自由に感想を述べたいと思います。

浅田 彰さん
撮影:御厨慎一郎
磯崎さんが説明されたように、建築や都市デザインの領域で、「環境」がキーワードとして浮上し、アートの領域でもカプローらが「環境」をキーワードとして提示して、それらが出会ったところで「空間から環境へ展」が企画され、その流れが万博までいくということですね。
その場合、たとえばケージの『4分33秒』だと、ピアニストが出てきてピアノの前でじっとしている、そういうハプニングこそがアートだ、ホールで聴衆がざわざわしたり外のノイズが響いてきたりする、そういう環境全体を含めてアートなんだ、ということになるでしょう。それこそ禅宗で、庭掃除で石を掃いてカーンという音がしたときに卒然として悟るなんていうのと、ちょっと似ているかもしれません。
そのケージも、一柳さんが言われたように他方ではエレクトロニクスを使った実験を試みるわけで、そうやってテクノロジーを使いながら、人間全体を包みこんで五感を刺激し、インタラクティヴに変化していくような環境――当時の言葉でいえば「サイバネティック・エンバイロメント」をつくろうという動きが盛んになってきた。山口さんも一柳さんも磯崎さんも、そういう流れのなかにおられた。それが特に大阪万博などでは大きくフィーチャーされたんですね。
さっきの三井館というのは、僕はあまり記憶にないですが、典型的には井口さんが紹介されたEATによるペプシ館があります。一方ではロバート・ラウシェンバーグのようなアーティスト、他方ではビリー・クルーヴァーのような破格のエンジニアが集まり、「Experiments in Art and Technology」、つまり「アートとテクノロジーの実験」をやろうということで、いろいろ実験を重ねていた。ペプシコーラがそれにのって、東京でも「クロストーク/インターメディア」のスポンサーをやったり、大阪万博でもペプシ館を任せたりした。しかし、当日はテクノロジーの限界があって、さまざまな音響(ケージの仲間だったディヴィッド・チュードアが来ていた)と映像が連動して人間を包み込む万華鏡のような空間というコンセプトは、必ずしも十分には実現できなかったんですね。ただ、考えてみれば、大阪万博のペプシ館がこんな前衛的な連中にやらせているということ自体、いまでは考えられない。そこから振り返ってみれば、「あの頃は、こんなテクノロジーしかなかったのに、こんなおもしろいことを考えていたんだ」というので驚くことは多いし、それを現代に生かすことも十分できるはずだと思います。
例えば大阪万博のペプシ館では、EATの仲間だった中谷芙二子さんが霧を発生させる実験を始めた。そこから、雪の科学者・中谷宇吉郎の娘である彼女が霧の芸術家になり、いろいろな活動を続けてきたわけですね。数年前に磯崎さんが設計された山口情報芸術センターで、その中谷さんの霧の作品が披露された。中谷さんはSCANというギャラリーを拠点としてヴィデオ・アートをずっとサポートしてきたので、そこで育った子どもにあたる世代の高谷史郎さん(ダムタイプ)が協力し、回転するミラーで霧の中に太陽光を投射するとか、高指向性スピーカーを仕込んだ回転柱を3×3のグリッドに並べ、チュードアが残したテープの音響を使ってインタラクティヴな音響場をつくるとか、いろいろな展開を試みたわけです。磯崎さんと僕も加わったトークもあって、たいへん面白かったのですが、そこでも言ったように、40年たって、やっと部分的に実現できるようになってきたような夢、アートとテクノロジーを組み合わせて全感覚を包摂するインタラクティヴな環境をつくろうという夢が、大阪万博の頃に不完全ながら提示されていたというのは、いまさらながら驚くべきことだと言えるでしょう。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
ついでに付け加えると、今も「飛鳥アートプロジェクト」の一環として中谷さんが石舞台で、で霧を発生させるパフォーマンスをやっています。石舞台の中に高谷さんが強力な照明を仕込み、霧で覆われた石舞台からパーっと光の矢が出たりする。YCAMのときほど複雑な試みではありませんが、古代の遺跡との取り合わせがとても印象的でした。
ともあれ、1960年代から70年代にかけて、「環境」という概念が建築・都市計画の領域でも芸術の領域でも同時に前景化されるようになった。そこには、山口さんが言われたように、単なる日常の一瞬がアーティスティックなもとして経験される、ケージのように、ピアニストが何も演奏しないことが音楽のハプニングになる、というような面もあったと同時に、アートとテクノロジーの出会いの中から、身体を丸ごと包み込み五感を刺激するインタラクティヴな環境をつくろう、という夢があった、それはいかまら振り返っても非常に面白いし、さまざまなヒントを与え続けてくれるものだと思います。
片岡:ありがとうございました。
メタボリズムも1960年の世界デザイン会議のために、若い建築家が日本的な何かを提示しようということで始まったと聞いていますけれども、その後、磯崎さんは、建築家の中で「不確定性」、それから「決定不可能性」というような、非常に東洋的な思想と関連が深いともとれるような概念を問題提起されています。磯崎さんのなかでの「環境」もしくは「エンバイロメント」という概念が、どのように発展をしていったかをお聞かせいただけますでしょうか。

磯崎 新さん(左)と一柳 慧さん
撮影:御厨慎一郎
磯崎:50年代の終わりごろというのは、ある意味で建築界も新しい流れ、CIAMというコルビュジエやグロピウスたちがリードしてやってきた。この動きに対して、次のジェネレーションはTeam X(チームテン)というふうに呼ばれていましたが、このTeam Xは新しい対抗的な思想を考えない。個々で出てきたコンセプトというのはせいぜい今でいうオバマの言っている「Change」と同じことですね。「Changeだ」、それから、「growthだ、成長だ」と、これも似たようなものです。つまり、ひとつのフィックスされた、固定された最終的な形態ではなくて、それが広がっていく、変わっていく、それから伸びていく、動いていく。こういうようなものが建築、あるいは都市のコンセプトの中に組み込まれていかないと。なかなか我々のこれからあとの時代というのはでき上がらないだろう、見えてこないだろう、それを具体化するのはテクノロジーだ。こういうことは、割と50年代の終わりごろ、60年前後に、だんだんはっきりしてきた。
僕は個人的に言うならば、もうこのときに、ジャクソン・ポロックのドリッピングのフィールドペインティングとジョン・ケージ、これは一柳さんの説明から学んだところですが、そういう「不確定性」、それから「偶然性」、アメリカのその後の、いわばニューヨークアートの始まりになる。このあたりの流れについては、「もう、そういうふうになるのだよ」と最初から受け取ってしまっていたのが、我々のジェネレーションでした。
その中から、何をどうやるかというときに、建築の中では都市問題が大きくクローズアップされてきた。ここで展覧会に出てくるメタボリズム、メタボリストと呼ばれているような建築家たちが、建築の側でありながら、都市について言う、都市について拡張した概念での提案をし始める、これがひとつの流れとして生まれてきた。私自身も、その流れにおいては同調して、同じようなことをやっていたというのが、この時期の最初のひとつです。
実は、僕はそれから10年ほどして、『建築の解体』という本をまとめたのです。ちょうど60年代になってから、アーバン、都市を含めた世界の建築デザイナー、あるいはシステムのエンジニア、こういう人たちがどういう新しい提案をし始めているのかということを、まとめてサーベイをやったのが、『建築の解体』として出版されました。

「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」展示風景
森美術館
撮影:渡邉 修
これを考えるきっかけというのは、このような流れ、動きが実は20年代は、ある意味でいうとバウハウスからCIAMというところを核にひとつの流れとしてあって、30年代はさまざまな別の問題が発生し、それを過ぎてみると、特に我々のジェネレーションというのは、いわばそこから散種、種が世界中に飛び散って、そしてその中で勝手な発想がいろいろなところで生まれた。
このひとつが、実はメタボリズムで、東京だった。それから、ロンドンにはアーキグラムというピーター・クックが中心にやっているグループがあって、さまざまな空想的なデザインをやり始める。ウィーンには、ハンス・ホラインという建築家が出てきて、これはピッヒラーと組んで、どちらかというとコンセプトそのもののような巨大な怪物、今でいうとリヴァイアサンと呼んでいいようなものが、街の中に突然出現する。これは一体どういうイメージなのか、空想的なイメージをだんだんつくり始めた。それから、フローレンスではアーキグラムやアーキズムというグループが、得体の知れない都市が突然、今の都市の中に洪水あるいは津波が入ってくるみたいに、ドーッとでき上がってくるという問題があるという、こういう絵を描き始めた。
これを我々、ロンドン、東京、ウィーン、3軸、3 axesと呼んでいましたが、のちにフローレンスを入れて「4 axesだ」というのを議論し始めた。実はこのときにフランスもアメリカもその軸に入れなかったというのが、我々のひそかな理解です。ということは、同じジェネレーションの連中が、つまり目の前にあらわれてこなかったというのが、60年代の状況です。

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
そういうことがいろいろ動いていくなかで、僕はこの「環境」の問題から個人的に言うと、山口さんと一緒に会社をつくって「環境計画」という名前をつけた。計画とは、近代社会がその進展の鍵にした方法概念ではあったのですが、60年代には終わりかけていました。もはや使えない。このときが使った最後です。
もうひとつ、ミラノ・トリエンナーレというところで、「エレクトリック・ラビリンス(電気的迷宮)」、というひとつのインスタレーションワークをやりました。僕は建築家としてかかわり、音楽は一柳さんにつくってもらって、写真のセレクションは東松照明がやってくれた。それをグラフィックに処理するのは杉浦康平がやりました。僕はいろいろな機械仕掛けや空間構成をやって、最終的には広島の廃墟、再び廃墟になった広島、展覧会の第1室にかけてもらっている、あの絵の原型をつくった。実はあれはスクリーンで、その上に未来都市プロジェクト、我々が60年代やったものを投影していた。当時でいえばマルチプロジェクションですが、そういう仕掛けをやったということがあります。
この仕事は、ある意味でいうと、違う領域のアーティスト、作曲家、写真家、デザイナー、建築家が組んでひとつの作品を組み立てて、今でいうとインスタレーションというように呼ばれている、内容的にはインタラクティヴな組み方、時間、空間的にインタラクティヴに観客と作者が入り乱れていく、こういう仕事をやり始めた。
僕にとってみると、「空間から環境へ展」というのは同時多発的にやっていた人が、ただ集まったことが始まりで、今度はそれをもうひとつ、いわば新しい空間というかエンバイロメントを組み立てていく。そのひとつの例として、たまたま68年、最初に「エレクトリック・ラビリンス」というものをやった。その辺の流れが、そのまま大阪万博のほうに組み立てて流れていった。これが、僕の60年代のつき合いですね。
ですから、ずっと考えてみると、都市のほうで万博の全体のプランをやったり、お祭り広場のコンセプトをつくったりというのは展覧会に出してもらっています。そのコンセプトとしては、いろいろな領域の人たちとお互いに共同し、しかもそれがだれの作品というのではなくて、全体としてひとつの環境として立ちあがっていくという仕事をみんなで考え始めたというように思います。
<関連リンク>
・シンポジウム「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」
第1回 「空間から環境へ展」とは
第2回 日常の意識を拡張する
第3回 建築、都市デザイン、政治から見た「環境」
第4回 大阪万博:テクノロジーと芸術の融合を試みた環境
<第5回 新しい時代に向けたヴィジョンとしての環境
・「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」
会期:2011年9月17日(土)~2012年1月15日(日)