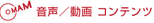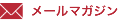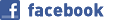1960年代~70年代のメタボリズムの全盛期には、建築や都市計画の分野だけでなく、美術や音楽などジャンルを超えた横断的な活動や交流が活発に行われました。建築が単体の建物から都市のインフラなども包括したメガストラクチャーへと拡張するなか、美術の分野でも表現のための空間は、「環境」あるいは「エンバイロメント」という言葉に置き換えられ、大きく拡張しました。2011年12月18日(日)に開催された「メタボリズムの未来都市展」第5回シンポジウムでは、「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」というテーマで、当時渦中にいた建築家、アーティスト、作曲家、あるいはその時代の研究者や批評家を招き、活発な議論が展開されました。その模様を連載でお伝えします。
連載(2)では、このシンポジウムの意義についての浅田彰氏による発言に続き、山口勝弘、一柳慧の両氏が1960年代当時のニューヨークの状況について語ります。山口氏の指摘する「日常性」、一柳氏の言う「今行っていることを正確に行う」ことは、日常の空間、音、現象、仕草、行為などへ意識を拡張したケージやカプローにみる禅の影響を想わせます。それはまた、より広い空間、森羅万象のなかで現在の自分自身の存在を意識するという意味で、「環境」の概念との繋がりを論じることもできそうです。
メタボリズムの未来都市 関連シンポジウム第5回「空間から環境へ」
2011年12月18日
[出演: 浅田 彰(京都造形芸術大学大学院長)、井口壽乃(埼玉大学教授)、磯崎 新(建築家)、一柳 慧(作曲家、ピアニスト)、山口勝弘(美術家) モデレーター: 片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター)]

左より磯崎 新さん、一柳 慧さん、浅田 彰さん、井口壽乃さん、山口勝弘さん
撮影:御厨慎一郎
浅田:ここで一言。モデレーター気質なので、モデレーターが言ったほうがいいかなと思うことを付け加えていいでしょうか、これは「メタボリズムの未来都市展」との関連のシンポジウムだけれども、この展覧会は建築と都市計画が中心になっている。そもそも、出発点のひとつとおぼしき八束はじめさんの一連のお仕事、特に『メタボリズム・ネクサス』は、都市工学的な面では、メタボリズムの源流から、その後の展開に至るまで、最近の研究もふまえてよく調べてあるけれど、理論的枠組みがはっきりしない(「超自我としての国家理念を体現すべき建築や都市が不気味なオルターエゴとして振る舞い始める」という話なら面白そうなのだけれど、それが明確にされていない)、また同時代の文化や芸術とのかかわりをほとんど見ていない(したがって磯崎新さんのような建築と芸術の両方に足を掛けていた人のポジションが明らかにされない)といった欠落がある。その点、この展覧会自体、「空間から環境へ展」を焦点として同時代の芸術との関係を示したところは大きな意味があると思うし、今日そのときの当事者である3人の方を交えて、こうしてお話ができるというのは、とても意義の深いことだと思います。その中で、この展覧会で問われているのが、単に建築・都市計画だけの問題ではなくて、芸術まで含めた広い文脈の中での問題だということが、いっそう明確になればいいんじゃないかというので、大変楽しみにしています。

京都造形芸術大学大学院長 浅田 彰さん
撮影:御厨慎一郎
それから、最初に井口さんがとてもうまく、包括的な文脈を提示してくださってよかったと思うのですが、そもそも、「空間から環境へ展」というときに、「環境」という言葉がどこから来たのか、椹木野衣さんが「浅田孝の『環境』概念からきた」というふうに言ったのが正しいかどうか。それはアカデミックな問題としては重要かもしれないにせよ、本質的には建築・都市計画でも、芸術でも同じようなことを考えていたと見ておけばいいと思うんです。
つまり建築・都市計画の文脈でも、日本が満州から南洋まで進出した頃から「環境」というのがキーワードとなり、戦後も南極の昭和基地のプレハブ建築をつくったりした浅田孝らはそれを強く意識していた。と同時に、芸術の文脈でも、フルクサスなどを筆頭にハプニング(今でいうパフォーマンス)が行われるようになり、ハプニングの生起する場をアラン・カプローなどが「ENVIRONMENT」と呼んで話題になった。こうして建築・都市計画において「環境」と芸術の文脈での「環境」がつながって、「空間から環境へ展」という展覧会が成立した。もちろん、「環境」という言葉の起源をめぐる井口さんのアカデミックなお話はそれでいいのですが、ここで話を進める上での了解としては、「環境」概念がどこから出てきたかを問うよりは、今言ったような同時平行性を想定しておけばいいのではないかと思うんです。というところで、まずは当時者である三大巨匠の話を承りたいと思っています。
片岡:それでは次に山口さんのご意見を伺いましょう。山口さんは井口さんから紹介のありました「エンバイラメントの会」の立ち上げにも関わっていらっしゃり、「空間から環境へ展」の企画にも携わっていらっしゃったということで、それがどのような背景で始まったのか、なぜ宣言文では「ENVIRONMENT」という言葉がアルファベットのままになっているのか、日本のなかでその言葉の概念自体を模索されていたのかなど、そのあたりの状況を当事者として教えていただければと思います。

美術家 山口勝弘さん
撮影:御厨慎一郎
山口:初めてニューヨークに行ったときに、2人の非常に重要な人と会いました。1人はオノ・ヨーコさん、もう1人はフレデリック・キースラーで、この2人から、僕はかなり影響を受けています。
簡単にいうと、「エンバイロメント」という言葉のなかに、僕はもうひとつ、「日常性」というキーワードを考えたほうがいいと思うのです。オノ・ヨーコ、アラン・カプローという当時、ニューヨークでハプニングをやっていた人たちのなかにあるのは、非常に日常的な人間の行為、しぐさ、そういうものから発生するものを評価していこうとする点で、そこが大事だと思うのです。
そういう「日常性」でいうと、キースラーは建築家ですが、建築家でありながら、非常に幅広い視野で、自分の作品を「環境」として考えていた人です。
オノ・ヨーコは、もちろん有名なフルクサス・グループの中心的な役割を果たした人です。オノ・ヨーコさんと会ったきっかけは、そのころ僕の実験工房の友達の花柳寿々紫さんという舞踊の人がニューヨークにいたのですが、寿々紫さんは、僕がニューヨークにいることを知って、「1人、山口さんに紹介したい人がいる」、それがオノ・ヨーコさんだったのです。オノ・ヨーコに会ったところ、彼女はフルクサスというグループを統率していました。アラン・カプローもそのころ、ニューヨークにいて、グリーン・ギャラリーというところを中心に活動の拠点を置いていたので、それを見に行きました。
どういうことをやっていたかというと、人が2人出てきて、柔道のまねごとみたいなことをするのです。それから、もうひとつは、女の人が出てきて、フライパンの上でバナナの切ったものを焼いている、要するに調理をする場面。それが、アラン・カプローのグリーン・ギャラリーのパフォーマンスでした。それで僕は先ほど「日常性」という言葉を使ったのですが、オノ・ヨーコのフルクサス・グループも、ロバート・モリスをはじめとして、彼らがやっていることを見ると、特別な演奏とか特別な音楽をやるのではなくて、非常に日常的な行為のなかから出てくる音を拾っています。
それはジョン・ケージもやっていたのですが、ジョン・ケージの作品の中にあるのも、「日常性」です。ジョン・ケージが日本に来て、先ほど話に出たように草月アートセンターでも彼は演奏しました。

シンポジウム『空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博』風景
撮影:御厨慎一郎
もう1人のキースラーという人に、僕はなぜ興味を持ったかというと、彼はウィーンにいて建築家になった人ですが、キースラーの考えたことは非常に先走った建築の考え方で、最後、彼は「エンドレスハウス」という計画を発表していました。僕はニューヨークのレオ・キャステリのクリスマスパーティでキースラーに初めて出会いました。キースラーの家に行くと、「お前は俺の何が見たいのか?」と聞かれたので「すべてだ」と言ったのです。
彼は建築の図面も書くし、それから、もちろん建築中のプロジェクトもあった。ところが、その次から彫刻に凝り始め、彫刻を盛んにつくっていました。それを部屋に展示しながら、「俺の作品は非常に空間的な展示をやる」と、天井から作品をぶら下げたり、それから壁に彫刻の一部をぶら下げたり、展示を床に置いた作品、「その三つが関連した俺の彫刻なんだ」ということを、これもやはり建築の基本的な要素、壁と床の展示、その関連付けを彼は彫刻でやろうとしていたのです。
そういう2人のアーティストに会った、これがニューヨークでの収穫でした。と同時に、先ほど申し上げた「日常性」ということでいうと、オルデンバーグというポップ・アーティストが、「The shop」、お店という店をやっていました。その店はニューヨークのダウンタウンにあって、彼に連れて行かれたところはお店ですが、お店の中に並んでいるのは、彼がつくった、段ボールとペンキでつくったお菓子の模型です。それはポップ・アートのはしりで、そこで彼は売っていたのです。日常的な場所に自分のアトリエを構えて、そこをお店にしてしまうという考え方は、やはりポップ・アートの中にある「日常性」ということのあらわれだと思います。
片岡:「エンバイラメントの会」の話を少ししていただいてもいいですか。エンバイラメントという言葉は、カプローから影響を受けたというふうにおっしゃっていたと思うのですけれど。
山口:いや、カプローから借りたのです。僕は、時代的に「日常性」という思考があったので、いわゆるジョン・ケージもそうだし、フルクサスがやっていることも全部日常的な行為であって、それをパフォーマンスと言っていたのです。
片岡:では続いて、アラン・カプローとも一緒に活動をされ、そしてジョン・ケージとも非常に近いところにいらっしゃった一柳さんに少しお話をいただきましょう。1950年代からニューヨークにいらっしゃって、既存の西洋の直線的な音楽の考え方に対して、当時は「時間という概念をどうするかということが議論になっていた」とおっしゃっていましたが、「エンバイロメント」の概念に関連して、そのあたりのことを教えていただけますか。

作曲家、ピアニスト 一柳 慧さん
撮影:御厨慎一郎
一柳: 山口さんは「日常性」とおっしゃいましたが、確かに「日常性」は、あのころ、ひとつの大きなテーマではありました。ただ、今まで出てこなかったことがひとつありまして、それは何かというと「日本」なんですよ。あるいは「東洋」といってもいいかもしれません。ジョン・ケージの「日常性」や、あるいは彼がやってきた普通には「偶然性」とか「不確定性」とか言われているような、音楽の土台になっているのは、実は日本が非常に深くかかわっています。
エピソード的な面をお話ししたいと思うのですが、あの当時は、日本はまだ戦後であったし、芸術というとヨーロッパやアメリカということで、そちらに注目が集まっていて、「日本」なんて言い出すと、私は批評家からかなりやられました。「ケージが日本と絡まっている」ということを言うと、実は秋山さんも「非常に心外だ」ということをおっしゃったのです。
ケージが劇的な転換をしたのは1950年代の頭でありまして、だれによってかというと鈴木大拙です。大拙は1949年、ニューヨークのコロンビア大学から招聘されて、禅の講義をしばらくやったということがありますが、この講義の影響というのは非常に大きいものでした。ケージが実際に劇的な転換をして、今までないような発想で、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、「無の音楽」と呼ばれているような、『4分33秒』という発想をつくったのも大拙がいたからで、そうでなかったら、恐らく出てこなかったであろうということです。
それともうひとつ、話を整理できるかどうかわかりませんが、当時のアメリカはほとんど唯一の戦勝国でした。もちろん、ロシアも勝ったし、フランスやイギリスも勝ったのですが、実際にはこういう国は日本でいうと沖縄みたいに自分の国が戦場になったわけですから、戦勝国といっても非常に戦後は貧しかったのです。そこで余裕があったのはアメリカだけでした。
そういうことが影響しているかと思いますが、つまりアメリカでは戦後の超高層ビル、ハイウェイのネットワークがどんどんできてきて、いわゆる文明の先端を推し進め、あるいは評価する人がいたのですが、その半面、そういうものに対する批判も非常に強かったです。
ケージなどと一緒に行動していると、私も、そういう批判を随分聞きました。それを文明の先端的なものに対して、何といっていいかわかりませんけれども、言葉がいいかどうかわかりませんが、「自然回帰」とでも言ったらいいでしょうか。

作曲家、ピアニスト 一柳 慧さん
撮影:御厨慎一郎
ジョン・ケージは、私が初めて会った1958年には、ニューヨーク州のストーニー・ポイントという、ニューヨーク市から1時間ぐらい行った山の中とでも言ったらいいでしょうか、広大な敷地にいました。これは1950年代の初めにブラック・マウンテン・カレッジという前衛のアカデミーをつくったポール・ウィリアムスという人がスポンサーになってケージたちに土地を開放して、先ほどちょっと話にも出ましたが、69年の「クロストーク/インターメディア」に来ましたスタン・ヴァンダービークとか、ピアニストのデイヴィッド・チューダー、これはケージの片腕と言われ、新しい作品をほとんど全部初演した人ですけれども、そういう人たちとケージとが一緒になって芸術村をつくり、その芸術村に一緒に住んでいました。本当に何もないところで、あったのは、丘というか山、それから川が流れているようなところで、土地としてはかなり広い土地です。
私は、実はケージに随分つき合わされたので、そちらの面も、かなり強調されて印象にありますが、つまりケージはそこに住んでほとんどの時間を作曲と、それからお得意のマッシュルーム、キノコ狩りに費やしていたのです。ですから、毎日、日本のお百姓さんが背負うようなカゴを背負って、自分の広大な土地をチューダーなどと一緒にめぐり歩いてキノコをとってきていました。彼はキノコでは世界の五指に入るキノコ学者であります。私はケージからさんざんキノコを食べさせられて、50種類以上のキノコを食べましたけれど、かなり危険なことですよね(笑)。でも、幸いにして当たらなかったです。
ケージは、60年代の後半からリウマチになりました。キノコとか、野生の野菜とか果物とか、お茶にする葉っぱなども、彼は全部自分たちの土地からとってやっていまして、そういうものは、ご存知のように非常にあくが強いので、そのあくが強いのを毎日、彼は自分で料理していた。その結果がリウマチじゃないかと私は思っているぐらいです(笑)。
ともかく、片方に完全に自然指向、もう片方に文明の先端指向の両方を持っていたのがケージです。先ほど出てきたフルクサスの人たちは、あまり自然指向はなく、非常にラディカルで、そのラディカリズムが芸術のうえだけじゃなく、政治とか社会問題にも出ていました。

シンポジウム会場風景
撮影:御厨慎一郎
ここではっきりさせておきたいと思いますけれども、正直言ってケージとフルクサスは仲が悪かったです。ケージはもっと芸術的でポエティックな人です。
フルクサスの首謀者といいますか、最初の創始者というのはジョージ・マチューナスで、この人はリトアニア出身です。どんなラディカリズムだったかというと、彼は「AGギャラリー」というギャラリーをマディソン・アヴェニューにつくりました。ここで新しいものをいろいろやっていて、それはそれでよかったのですが、アメリカの東京電力、コンエディソンという会社ですが、「コンエディソンという電力会社に対して電気代を一切払わない、アーティストとしては当たり前のことだ」とガス代も払わない。夕方になると暗くなってきますから、画廊は4時ごろには閉鎖しないと何も見えなくなってしまう。ニューヨークの冬はめちゃくちゃに寒いのですが、その寒さのなかでガスもなく、ストーブもなく、電気もなくという生活を貫く。そんな形の人でしたので、ちょっとケージはついていけなかったと思うし、私もどちらかというとケージのそばにずっといました。
私が申し上げたかったのは、ケージは非常に文明の先端的な、例えば、ライブ・エレクトロニクス・ミュージック、ライブ・コンピュータ・ミュージックを先導してやった人で、これがのちのインターメディアにつながる流れだったと思います。他方で、非常にナイーブな自然回帰的な生活をしていた人であったということです。
ケージの家には家具が一切ありませんでした。つまり彼は鈴木大拙から教えられた教えというものを、私ははっきりした言葉として覚えていなくて恐縮ですけれども、「今、ここにあるということが最も大事だ」というのが鈴木大拙のひとつの言葉だったと思いますが、それと似たような言葉で、「今行っていることを正確に行う」ということがケージのモットーとしてあったのですね。普通だったら芸術家も生活まではなかなか変えません。「日常性」というのは、確かに山口さんがおっしゃったけれど、やはり家に帰ればテレビを見て寝転んだり、お酒を飲んだりとかいろいろします。しかし生活まで変えてしまって、しかも家具も家の中に持たないというようなところまで徹底して、音楽と同じように厳しく考えて生活した、そういうところは非常に強い印象として、私には残っています。
片岡:ありがとうございました。「日本もしくは東洋からの影響」という部分については、非常に関心がありますので後でもう少し聞かせていただければと思います。
<関連リンク>
・シンポジウム「空間から環境へ:同時代のインターメディアな活動と万博」
第1回 「空間から環境へ展」とは
第2回 日常の意識を拡張する
第3回 建築、都市デザイン、政治から見た「環境」
第4回 大阪万博:テクノロジーと芸術の融合を試みた環境
第5回 新しい時代に向けたヴィジョンとしての環境
・「メタボリズムの未来都市展:戦後日本・今甦る復興の夢とビジョン」
会期:2011年9月17日(土)~2012年1月15日(日)