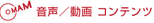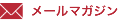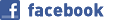世界で活躍するアーティストやキュレーターをゲストに迎え、ホットな話題を議論する森美術館の人気企画「アージェント・トーク」。2013年1月に開催した「アージェント・トーク017」では、なぜいま、アメリカで日本の戦後前衛美術運動が注目を浴びているのか――「もの派」の研究者であり、ハーシュホーン美術館・彫刻庭園のアシスタント・キュレーターである吉竹美香氏に、ご自身の研究や展覧会の紹介をふまえ、1970年代の貴重な記録映像の紹介も交えて詳しくお話をしていただきました。

吉竹美香
撮影:御厨慎一郎
2012年、吉竹氏はロサンジェルスのBlum & Poeギャラリーで、「太陽へのレクイエム:もの派の芸術」と題した展覧会を企画した。これは近く出版される、戦後の日本美術における重要なターニングポイントとなった「もの派」という芸術運動を、作家の実践と批評家の理論双方から再訪した彼女のUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の博士論文に基づき、リチャード・セラ、エヴァ・ヘッセのような作家たちを代表とするポスト・ミニマリズムの実践に、「もの派」がどのように呼応しているのかを探るものだ。

Courtesy of Blum & Poe, Los Angeles
展示では李禹煥、関根伸夫、菅木志雄、吉田克郎、成田克彦、小清水漸と、「もの派」を代表する作家による作品が、渡米した作家たち自身と吉竹氏のアレンジによってギャラリー空間に併置され、図録では作家の著作も英訳され紹介されている。「もの派」の多くの作家が制作に取り入れた反復という行為や作品の一過性という美的言語、あるいは「もの」に関わる構造の関係性を提示しつつ、「もの」を操作し固有の作品を創造する作家の主観性、もしくは作家-物=主体-客体という関係性を徹底的に拒否する態度とその哲学を、多角的に示唆している。
この展覧会以外にも、2012年11月から2013年2月まで、ニューヨーク近代美術館で「東京:1955-1970」と題した展覧会が開かれ、戦後の日本の前衛美術が300点にも及ぶ作品群が紹介された。また、2013年2月から5月までは、ニューヨークのグッゲンハイム美術館で、1950年代に関西で結成された前衛美術グループである具体美術協会を取り上げた、「具体:素晴らしい遊び場所」展が開催されている。
日本からこの状況を眺めると、なぜいま、アメリカにおける日本の戦後美術への関心がにわかに高まりつつあるのかという疑問が生じるのは不思議ではないだろう。しかし吉竹氏は、このような大型企画が次々と実現したのは必ずしも偶発的な現象ではなく、むしろアメリカの美術館が日本の戦後美術のコレクションと研究を数十年間蓄積してきた成果の現れであるという。一例を取り上げると、ニューヨーク近代美術館(MoMA)は2,000点以上の日本の戦後美術のコレクションを所蔵し、1966年に開催した「新しい日本の絵画と彫刻」展や、1970年代に行った日本のビデオアートの紹介など、早くから日本の現代美術に関する展覧会を催してきた。
また、戦後日本の前衛運動に関する重要な展覧会としては、1994年、現グッゲンハイム美術館アジア美術部門のシニア・キュレーターであるアレクサンドラ・モンロー氏の企画により、グッゲンハイム美術館、サンフランシスコ近代美術館で開催された「Scream Against the Sky」展がある(日本では横浜美術館にて「戦後日本の前衛美術」展と題して開催)。ここでモンロー氏は、日本の前衛美術運動は、西洋のそれをそのまま取り入れた模倣ではなく、むしろ東/西の二項対立を拒絶しながらアジアの特殊な世界観を具現化したものとして、その思想的基盤には文化的ナショナリズムがあると提示している。

左:片岡真実、右:吉竹美香
撮影:御厨慎一郎

会場風景
撮影:御厨慎一郎
これだけ大きな規模での戦後日本美術に関する展覧会は、その後長い間取り上げられることはなかったが、その間に、前衛の時代を実際に経験していない吉竹氏のような若手の研究者やキュレーターが、前世代の築いた研究基盤を大きく発展させたということは間違いないだろう。その背景には、ここ数十年の間で現代美術をとりまく組織――主に大学や美術館などの研究機関――が、日本を含めた非西洋圏の美術、哲学、歴史を把握する重要さを認識し、「もの派」のような、これまで西欧中心の「美術史」を成すメインストリームの外におかれていた美術運動についての研究を活発に行うようになったという状況がある。その一方で、吉竹氏や国をまたいで活動する人々が、その語学力を活かして前世代がアクセスしえなかった資料を緻密に調査し、作家たちと直接ネットワークを築いてきたという成果もあるだろう。
ダイナミックに変動した社会に対峙した作家たちの実践や実験を、約40年という時間を経てより客観的に見つめるとき、そこにどのような新しい意味や価値を見出しうるのであろうか。また、その時代を垣間見ることによって、「現代」がどのように立ち現れるだろうか。戦後日本の前衛美術運動をいま振り返ることで、現代の日本における美術の実践に対する、新しい解釈や可能性が開けることを期待したい。
文:崔 敬華(チェ・キョンファ)
吉竹美香(ハーシュホーン美術館・彫刻庭園アシスタント・キュレーター、ワシントンDC)

2012年春にUCLAの博士論文に基づいた「太陽へのレクイエム:もの派の芸術」展をロサンジェルスのBlum & Poeギャラリーで企画した他、グッゲンハイム美術館での「李 禹煥」展(2011)、ロサンジェルス現代美術館の「村上隆」展(2007)にも携わり、カタログに寄稿。また、「東京1955-1970:新しい前衛」(ニューヨーク近代美術館、2012)、「ターゲット・プラクティス」(シアトル美術館、2009)のカタログにも寄稿している。
<関連リンク>
・アージェント・トーク008理想の未来像を描くことは簡単ではない 映像プログラム「スター・シティ」を上映
・アージェント・トーク009
ニナ・フィッシャー&マロアン・エル・ザニの映像作品に見る「歴史への視点」
・アージェント・トーク010
アート顧客拡大に向けたデジタル・メディアの効用法‐英国テートの例
・アージェント・トーク011
アジアの歴史的な美術や文化を現代に繋げる。サンフランシスコ、アジア美術館の進む道 ・アージェント・トーク013
世界最大の現代アートの祭典DOCUMENTA 13速報 存在感を出していたのは身体的な感覚に訴えかける作品 ・アージェント・トーク014
レアンドロ・エルリッヒ 視覚のトリックで現実を問い直す