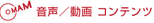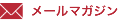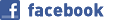4月30日に実施された、森美術館「LOVE展:アートにみる愛のかたち」と白金アートコンプレックスの合同展覧会「メメント・モリ 愛と死を見つめて」との連動企画によるトークセッション。スピーカーは、「LOVE展」出展アーティストであり、「メメント・モリ 愛と死を見つめて」展のゲストキュレーターの杉本博司氏と、批評家の浅田彰氏。
愛とエロス、愛と死、そして愛の可能性について熱く論じたその様子を"フクヘン"の愛称でおなじみの美術ジャーナリスト・鈴木芳雄さんによるレポートでお届けします。

森美術館開館10周年記念展「LOVE展」関連イベントでゲストは杉本博司と浅田彰。杉本博司といえば開館2年目(2005年)にここで大規模な個展を開催し、それまで欧米での活躍ぶりに比して日本ではもうひとつ知名度が低かった彼が、一気に祖国に錦を飾った展覧会になった(当時、雑誌『ブルータス』がまるごと1冊、杉本特集を組んだ...というか僕が作りました)。今回の「LOVE展」でも出展作家の一人である。一方の浅田氏は美術大学の要職にも就いている、美術界の論客。森美術館の活動については開館時からウォッチしている。

杉本博司氏

浅田彰氏
そんな二人が特別展の公式イベントで公開対談をするというのは、至極まっとうでいかにもありがちなテッパン企画に見えるかもしれない。しかし、実はここで対談をすることになったいきさつは全然違う。それについてはのちほど書くが、ともかく、この大御所二人の対談。急に決まって、展覧会のサイトで観客募集のお知らせをしたところ、あっという間に埋まってしまい、悔しい思いをした人も多かったようだ。

講演を実際に聞いたある人にその内容について聞いてみるとたとえばこんな説明がされるか。
「《階段を降りる裸体》でスキャンダルを巻き起こしたマルセル・デュシャンはその後、絵画を放棄し、レディメイドのオブジェなどを中心とする独自の表現へと向かうが、彼が『網膜的絵画の創始者』として批判したギュスターヴ・クールベのことを実は最後まで強く意識していた。とりわけ、のちにジャック・ラカンが所蔵した絵画《世界の起源》には嫉妬ともいえる思いを抱いていた(ラカンはこの特別な絵を、義兄であるアンドレ・マッソン描く暗号のような絵で覆ったという)。のちに、デュシャンは遺作《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ》でその感情に区切りをつけられただろうか」
ふうむ。そうなのか(よくわからない)。常日頃、デュシャンピアンを自称する杉本ではあるが、さすがに浅田彰、杉本博司の対談、いきなり、近代美術を彩った美術家の名が引用されてくる。
さて、講演を聴いた、もう少し、事情やそれぞれの作品がわかっている別の人はこんな説明をするかもしれない。
「《透明アクリル製の跳び箱が与えられたとせよ。》とでも言おうか。その中には男性が一人入れる。ノーパンの女性がこの跳び箱を跳ぶ瞬間を仰ぎ見るわけだ。滑空する女性器。それは、クールベ、デュシャンとつながっていく。クールベの《世界の起源》という女性器だけをアップで描いた絵がオルセー美術館にある。しかも一時所有者は哲学者ジャック・ラカンだったという華やかな経歴。そしてクールベを意識していたデュシャンの遺作はというと、トビラに開けられた穴を覗き込むと裸の女性がしどけなく横たわりガス灯を掲げる《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ》。話の発端となった《ノーパン跳び箱》の作者はパリのカルティエ現代美術財団や東京オペラシティアートギャラリーで堂々の個展を開催した「現代美術家」北野タケシである。近代の美術家たちが追い求めた女性の裸、とりわけ極点を究めようとした系譜はここに繋がっている。そしてそれは一つのLOVEの具体的着地点(行き着くところ)かもしれない」

そう考えた(かどうかは知らないが)杉本と浅田は「LOVE展」にこの作品が必要と判断し、聞くところでは磯崎新まで巻き込んで盛り上がり、森美術館に推薦したが、やんわりと拒否され、出品成らなかったらしい。
結局、杉本はどうしたかというと、白金のギャラリーコンプレックスビル全館を使い、通称「裏LOVE展」=「メメント・モリ - 愛と死を見つめて - 」をキュレーションし、この跳び箱も展示したのである。ちなみに「メメント・モリ」は文字通りの「死を想え」と「森(美術館)を想え」とが掛けてあることは言うまでもない。
そんなわけで、一時はライバル的関係の展覧会(とは白金側の一方的思い込み?)だったが本編の森美術館の場を借りて、思いを語るチャンスとしてもこの二人のトークが実現してしまった。
このお二人、哲学者たちの言説を引きつつ、いっきに個人的な体験に落とし込むなど、聞いているこちら側がその落差についていくために、心していないといけない。

こんな話までしてくれた。若くして結婚した杉本の母は性行為と妊娠の関係について無知だったという驚きの事実と、人間は宗教と芸術とエロティシズムを俗の世界を超越する聖なる領域と規定したというジョルジュ・バタイユの論説。具体的に言えば、杉本を妊娠・出産した母の驚くべきイノセントぶりと、一方、バタイユの語る性は隠されることによって欲情され、聖性は汚れへの恐れゆえ崇拝されるという人間の性(さが)であると対比する。
それを受けて、浅田は「処女懐胎」を語り、ヘーゲルの論理を語るアレクサンドル・コジェーヴとかいう人のことを引き合いに出す。この人、サルトルやメルロ=ポンティ、ラカン、そしてバタイユの先生なのだそうだ。
そして、バタイユから岡本太郎、岡本太郎とくれば「芸術は爆発」、太陽の塔、太陽の塔から丹下健三、磯崎新に至る(つながる)。そうかと思うと、杉本は少年時代、セミプロの落語家だった父に連れられて行った寄席で聞いた古今亭志ん生の艶笑落語を記憶に頼りながら復活させ演じてみせる。浅田が初音ミクのようなヴァーチャルなアイドルが理解できないと言い出せば、杉本はすかさず「あなたも新人類と言われたはずなのに」とツッコミ、会場は爆笑。
さて、展覧会全般について、杉本は「おもしろいものは、そうたくさんはない」と言い切ってしまっている。一方の浅田は苦笑しながらも「僕はたくさんありますよ」。
杉本の好みを最も惹いたのはローリー・シモンズのラブドールを使った作品のようだ。その人形のハイテクさと作品が伝える無機質的なエロスを現代の若者、いわゆる「草食男子」現象に重ねながら、反応している。

出展作家でもある杉本は、自身がプロデュースした文楽「曾根崎心中」のために復活させた一人遣いの《お初人形》とそのお初が信仰する観音の具体的イコンとして、平安時代に作られた《十一面観音像》を出品しているのだが、彼は文楽の「前口上」でこんなことを述べている。
「我が国においてエロスの問題、つまり色恋沙汰は、詩的関心事ではあっても、長らく宗教的な関心事ではなかった。しかし恋を心中によって成就させることによって、二人の魂が浄土へと導かれるという革命的な解釈が、はじめて近松門左衛門によって披露されたのが、この人形浄瑠璃『曾根崎心中』である。」
日本と比べ、ギリシャ・ローマ神話から始まる西欧の方が、色恋とエロスを宗教的な関心事としていることは、ローマ神話の主神ユーピテル(ギリシャ神話ではゼウス)や愛の美神ヴィーナス(ギリシャ神話ではアフロディテ)の営みを挙げればわかりやすい。愛とは本来肉体的なものだという考え方は西欧圏で支配的なのである。
白金で杉本がキュレーションをしたメメント・モリ展(すでに終了)がエロスとタナトスにどっぷりと踏み込んでいるのに対して、森美術館のLOVE展は大きく人類の愛をテーマにしている対比がある。
LOVEは、カラダの問題なのか、ココロの問題なのか。
このトークイベント、出展作家代表と気鋭の論客という、誰もが考えそうで最もありがちなコンビに見える二人を揃えること、それは実は、最も危険で、やってはいけなかった(?)、でもどうしても聞きたかった組み合わせだったという結論。そこはそれ、そうなのだが、ここは浅田が引いたヘーゲルの論理で片がつくだろう。
「否定は来たるべき肯定のためのプロセスにすぎない」。
文・鈴木芳雄(美術ジャーナリスト)
撮影:御厨慎一郎
<関連リンク>
・六本木ヒルズ・森美術館10周年記念展
「LOVE展:アートにみる愛のかたち-シャガールから草間彌生、初音ミクまで」
2013年4月26日(金)-9月1日(日)
・7組のアーティストたちによる愛のかたち。
(前編) 愛は壊れやすいもの、でも期待せずにはいられない―チャン・エンツー
(後編) 人をどう扱うか、それが国や社会への物差しになる―アルフレド・ジャー