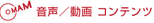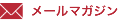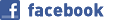現在開催中の「MAMプロジェクト018:山城知佳子」展。その関連イベントとして、山城作品の制作と発表に携わった二人のキュレーター、東京国立近代美術館の鈴木勝雄氏と本展を担当する森美術館の近藤健一による対談が行われました。初期作品から新作《肉屋の女》(2012)まで、画像や映像を交えながら作品をめぐる様々な意見交換がなされました。

左:近藤健一(森美術館キュレーター)、右:鈴木勝雄(東京国立近代美術館主任研究員)
撮影:御厨慎一郎
鈴木氏と山城の出会いは、鈴木氏が企画した東京国立近代美術館「沖縄・プリズム 1872-2008」展(2008)で、ここで山城は、後に彼女の代表作となる《アーサ女》(2008)を新作として発表しています。今回の対談はまず鈴木氏が同展のリサーチ中に見た山城の映像作品「オキナワTOURIST」シリーズの紹介から始まりました。

鈴木勝雄(東京国立近代美術館主任研究員)
撮影:御厨慎一郎

近藤健一(森美術館キュレーター)
撮影:御厨慎一郎
《オキナワTOURIST― I Like Okinawa Sweet》(2004)は、米軍基地のフェンスを背に山城本人が紅芋のアイスクリームを官能的な仕草で舐めまわし食べ続けるという作品です。この「女」が何の象徴なのかははっきりしませんが、「女」が「沖縄の象徴」だとすれば、女に挑発されるカメラ越しの「男性」は「日本・本土」や「米軍」であるとも考えられます。延々と消費されるアイスクリームは観光地としての沖縄、もしくは基地の見返りとしての補助金のようにもとれる、と鈴木氏は説明し、「(男=本土の人間として)『自分の見たい沖縄』を見ようとする視線を、『現実の沖縄はそうではない』とさえぎられたようだった」と振り返ります。

《オキナワTOURIST― I Like Okinawa Sweet》
2004年
ビデオ 7分30秒
Courtesy: Yumiko Chiba Associates
次に《オキナワTOURIST―墓庭エイサー》(2004)。墓庭とは沖縄特有の庭付きの墓で、祖先の死を悼む場でありながら親戚の集まりや祝宴に使われる交流の場でもあります。本作はこの神聖な場所で人々が沖縄伝統芸能のエイサーを踊る様子を、スローモーションで再生したものです。頭から白い紙袋をかぶった人々が間延びした音声に合わせて踊る姿は奇妙で滑稽にもみえますが、「見慣れているエイサーを遅い速度でみせることで、よく知っているはずの沖縄をもう一度見つめ直すことを、沖縄の人に促しているようにもとれる」と近藤はいいます。
タイトルにある「TOURIST(観光客)」からも想像できるように、本シリーズは1975年の沖縄国際海洋博覧会以降に定着した観光・リゾート地としての沖縄像を問い直す作品だといいます。また、この頃の沖縄アートシーンにおいて欠かせないのが前島アートセンターです。鈴木氏が「オキナワTOURIST」シリーズを見たのもこのアートセンターで、沖縄県立美術館の建設計画が凍結していた最中、発表の場を求めていた沖縄在住の若い作家たちによって2001年に開館しました。2011年の閉館まで沖縄の現代アートを支えていたこの施設で山城も作家としてのキャリアをスタートさせたのです。

《オキナワTOURIST―墓庭エイサー》
2004年
ビデオ 6分50秒
Courtesy: Yumiko Chiba Associates
2007年になると、山城は「戦争体験継承」をテーマに新たな作品制作に取り組みます。彼女は「戦争体験を自分のものとして理解しようとしたが結局わからなかった」という立ち位置で、《回想法》(2008)、「バーチャル継承」シリーズ(2008)などを制作。その後も、「語り」や「声」を通した継承の可能性について粘り強く挑みます。《コロスの唄》(2010)は、写真と床に投影された映像で構成されるインスタレーション作品です。木漏れ日の中に世代の異なる人々が触れ合っている様子が映し出されていますが、彼らの姿が光と影のコントラストによって唐突に分断され、性も年齢もわからない「肉体の断片」に見えてきます。コロスとは古代ギリシャ語で合唱隊を意味しますが、山城はこの「唄」は地面から聞こえてくる吐息や音だと語っています。作品には音がなく誰が何を唄っているのかは想像するしかありませんが、「地に眠る戦没者たちの声の響き合いとも解釈できる」と近藤はいいます。また、この作品が複数の「語り」や「声」のアンサンブルであり、そこにはどの「語り」が重要かというヒエラルキーは存在しないと、両者は加えました。
《コロスの唄》にみられる「肉体の断片」は、《肉屋の女》(2012)で複雑に表出します。この映像作品は、米軍基地敷地内の闇市にある肉屋の女主人を中心に、闇市近くの道路建設中の浜や鍾乳洞などを舞台に展開します。この浜は闇市と同様、日本政府からも米軍からも黙認されていた場所で、誰のものでもないユートピア的空間でした。

《コロスの唄No.18》
2010年
超光沢Cプリント
80×120cm
Courtesy: Yumiko Chiba Associates

会場の様子
撮影:御厨慎一郎
さて、この対談で特に注目されたのは、物語の中に読み取れる二つのカニバリズム(共食い)でした。一つめは建設現場で働く無気力な男たちが肉屋の女を食べるというもの。もう一つは、肉屋の女が別の肉屋の女を食べるというものです。前者について近藤は「沖縄に直結して考えると、沖縄の人々が沖縄の宝である自然を破壊し、雇用を生まなければ生きていけない=沖縄人が沖縄を食う=自分で自分を食うというカニバリズムにもとれる」と語ります。一方、後者は前者とは性質を異にし、「物語の中で激しい感情を露にする女たちによるカニバリズムは、インディオの習慣にみられる呪術的なカニバリズムに通じる」と鈴木氏はいいます。それは、食べ、食べられる行為によって、相手の力を受け取り、自分の力を分け与えるという力の伝播を生むカニバリズムです。他人の肉を食べること、他人に肉を食べられることは恐怖を伴いますが、肉を介したコミュニケーションでしか伝わらない何かがとても重要であると作家は考えているのかもしれない、と両者は対談を締めくくりました。
文:河上直衣(森美術館学芸部 アシスタント)
<関連リンク>
・「MAMプロジェクト018:山城知佳子」
2012年11月17日(土)-2013年3月31日(日)
アーティストトーク・レポート
・山城知佳子の沖縄
詩的映像が映し出す真実の姿