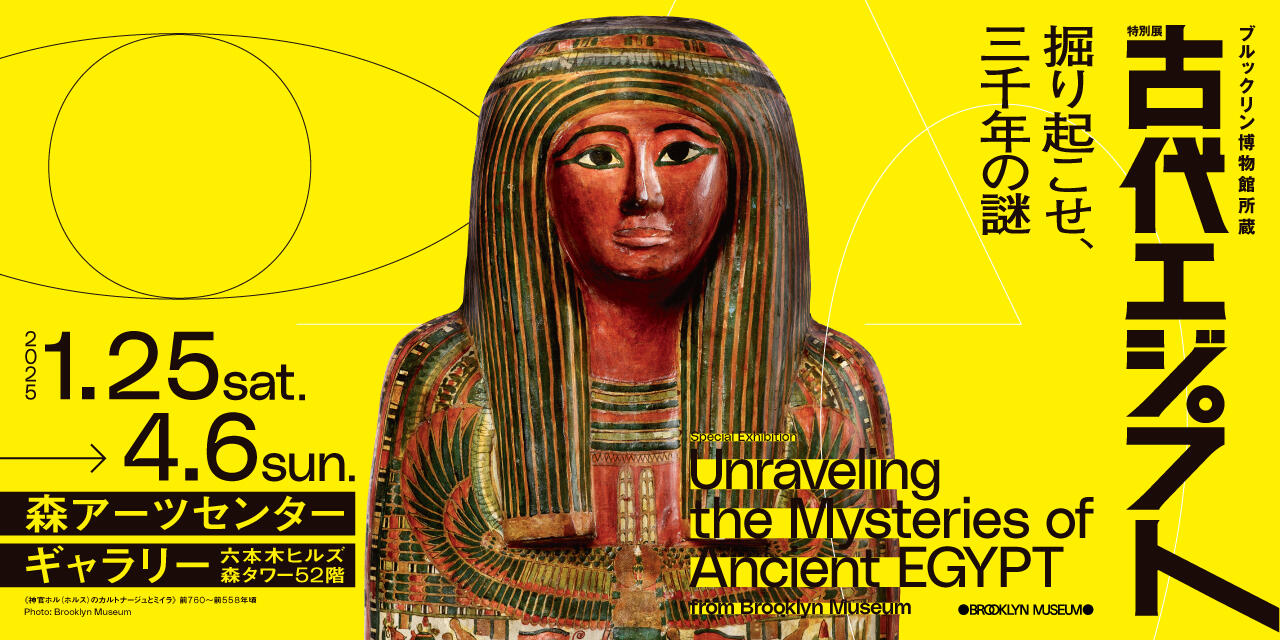森美術館と日フィルの音楽ワークショップ・シリーズEYES & EARS Vol.2「聴くことのリアル」を開催しました!
2018.7.17(火)
「見ることのリアル」から、「聴くことのリアル」を考えました
2018年2月6日、「レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル」の展示室内で森美術館と日本フィルハーモニー交響楽団による音楽ワークショップ「聴くことのリアル」を開催しました。今回のテーマは、「私たちが現実だと思っていることは本当に真実なのだろうか?」を共に考えることでした。

ワークショップの様子

マイケル・スペンサーさん
ワークショップの冒頭、マイケル・スペンサーさんが参加者に伝えたのは、人間はいかに「視覚」によって多くの物事を認識しているかということ。まず、一つの実験が行われました。マイケルさんの手拍子を手がかりに、アイマスクをしたまま彼の居場所を指差すというものです。音だけを頼りに会場内を移動するマイケルさんを指差す参加者たち。しかし、目を開けると彼はまったく予想外の場所にいました。同じリズムで他のスタッフが交替して音を出していたからです。聴覚だけが頼りという状況で、皆、集中していたにも関わらず、それをマイケルさんの手拍子だと「信じ込んでしまった」ために、容易に騙されてしまったのです。


さまざまな話題に引き込まれました
《試着室》で揺さぶられる感覚――真実とは何か?
続いて、参加者たちはファシリテーターと共に、「レアンドロ・エルリッヒ展」の鑑賞へ。作品を通してレアンドロが投げかけてくる、「感覚」や「認識」への揺さぶりを楽しみながら鑑賞しました。特に本ワークショップの題材となった《試着室》は、いくつもの小部屋が迷路のように入り組んでおり、中に入ると、「鏡には自分自身が映るもの」という先入観が根底から揺さぶられる作品です。「誰かと顔を合わせた時、相手をまるで自分のように感じる」「意図しないタイミングで、他者といろいろな感覚を味わう」。そうした参加者の感想に、あるファシリテーターは、作品の中で「知らない人が見え隠れする」感じが、今日の音楽作りにつながるところがあると語りかけました。

《試着室》(2008年)を鑑賞する参加者たち

《美容院》(2008/2017年)では自然と互いに笑顔が生まれました
再び会場に戻ると、指定されたアプリから各自の携帯に音をダウンロード。その音は種々の野鳥の鳴き声で、全員がアイマスクをして音を鑑賞しました。東京・六本木の森美術館から突如、イギリスの緑豊かな森の散策へ――。冒頭で体験したように、視覚を遮断されるだけで物事の認識に苦慮する人間は、しかし、聴覚と想像力だけでこのようなありえない旅をすることもできる――人の「イメージする力」の可能性にも触れた瞬間でした。
「見ることのリアル」と魔女狩りの物語
日常の中で日々の現実を自明のことと信じて生きる我々に、レアンドロは疑問を投げかけてきます。彼の作品は鏡や錯視の効果を生かしたものが多く、ユーモアに溢れる意外性のある体験を通し、人は自分の認識がいかに不確かなものであるかを感じることになるのです。しかし、自然と鑑賞者同士のコミュニケーションが生まれて笑顔や対話を生み出す半面、「思い込み」の根源に潜む人の欲望や、真実から目を背けようとする姿などが透かし見え、そうした人の醜い性質をもあぶり出す一面も持っているといえるでしょう。
マイケルさんは、次にスコットランド出身の作曲家ジェームズ・マクミラン(1959-)の楽曲《イザベラ・ゴーディの告白》に触れました。イザベラ・ゴーディとは、宗教改革よりも前の時代、ヨーロッパ全土で吹き荒れた「魔女狩り」の風習の中、自ら魔女であることを告白した女性です。スコットランドでは1560年から1707年の間におよそ4,500人の女性たちが魔女裁判にかけられ命を落としたとされています。なぜ、彼女らは命を落とさねばならなかったのか――人が人の噂を闇雲に信じるのではなく一人一人が真実は何かを見出せていれば歴史は変わっていたのかもしれない、とマイケルさんは語りました。この楽曲は、「イザベラ・ゴーディのために決して歌われることのないレクイエム」という別名があります。


音楽づくりが始まります
そのあと参加者たちは、この楽曲の一部に参加することになりました。スコットランド特有の音色が使われている楽曲で、それはバグパイプの音のような重層的な音です。これらの音に着目し、参加者たちはトーンチャイムなどの楽器で音を作りました。全員での演奏が終わると、マクミランのレクイエムが流れ、楽曲の一部を演奏していたことを実感しながらワークショップは終了しました。時代も地域も異なる世界に生きる私たちですが、その時、当事者だったとしたら私たちはどのような行動を取ったでしょうか。噂や迷信に惑わされず「真実」を見極める力や知性、勇気を持てるだろうか――マクミランの想いが参加者の心に響いた瞬間でした。


全員での演奏会
アートと音楽―視覚と聴覚のはざまで
本ワークショップでは、視覚と身体感覚を駆使してレアンドロ作品を鑑賞すると共に、視覚が遮断された時、聴覚によって物事を認識する難しさも体験しました。人の感覚はいかに脆弱で完璧ではないかということや、あたり前の認識を疑うことの大事さを学ばせてもらったように思います。また、アートだからこそ表現できるものがあるのと同様に、音楽も聴覚と豊かなイメージの力によってこそ成立する、稀有な芸術であると知ることができました。

マイケル・スペンサー、酒井雅代(通訳)、伊波睦(トロンボーン)、大澤哲弥(チェロ)、佐藤駿一郎(ヴァイオリン)、竹内弦(ヴァイオリン)、中川裕美子(ヴィオラ)、星野究(トランペット)とスタッフも《建物》(2004/2017年)で記念撮影
「宇宙と芸術展」(2016年)以降シリーズ化した音楽ワークショップのシリーズ名は「EYES & EARS(目と耳)」。見る場である美術館と、聴く場を創る交響楽団は、異分野でありながら多くの共通点を見出すことができます。例えば、プロフェッショナルが集い、切磋琢磨して生み出す非日常空間に鑑賞者を迎えることや、文化の歴史的な軸の上に立って、古典からより先端的な現代表現に向き合いながら、クリエイティヴィティの意味や思想を伝える使命を担っていることなどが挙げられるでしょう。芸術を題材に思考し、学び合い、共有する方法は一つではありません。今回のワークショップも一つの実験であり、森美術館では今後も多様な企画を、さまざまな人たちと共に模索していきたいと考えています。
文:白濱恵里子(森美術館アソシエイト・ラーニング・キュレーター)
撮影:田山達之
※ワークショップの記録映像公開中:こちら
タグ