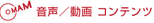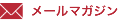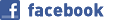江戸時代から現代にかけて、日本人の"自然観"は西洋の近代科学的思想に影響され、どのように変化してきたのか?様々な角度から日本の自然観を考える「ネイチャー・センス展」の関連プログラムの一つとして、レクチャー「近代日本自然観の成立」が11月3日(祝)に開催されました。講師は、本展のカタログにも論考を寄稿いただいたロンドン芸術大学、チェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン教授、トランスナショナル・アート研究所所長の渡辺俊夫先生です。

実例を交えたとても分かりやすいお話に、参加者も熱心に耳を傾けていました。
日本人は自然を愛好する―これは日本文化を語るときにしばしば語られるステレオタイプの一つです。現在では当然のように使っている「自然」という言葉が、日本で普通に使われるようになったのは1930年以降に過ぎないのだとか。英語の「nature」の訳語として当てられた1880年代から、1930年代までこの語義は大きく揺れ動いたといいます。
そもそも日本で自然の概念を指すには、万有、森羅万象、天然、などの用語が使われ、人間はその中に包括されているという捉え方でした。しかし、西洋の言う自然とは人間活動とは全く別のもので人が関与できるものではなく、日本とは正反対の考え方をしていたのです。
1880年以前の江戸時代の日本では、名所図会(めいしょずえ 諸国の名所旧跡が記された地誌)などの浮世絵に描かれる自然景観には人や寺社などの文化的要素を含む描写が不可欠であり、それが自然を描く主流となっていました。一方で、そのような文化的要素を排除し、客観的・地理学的観察のみに基づいた景観を描く傾向も出てきたこと、江戸後期には科学的観察と調査に基づいた博物図譜や日本地図などの製作が盛況だったこと、などの背景も同時に存在していました。

葛飾北斎 《富嶽三十六景 凱風快晴》
客観的・地理学的観察に基づいた浮世絵の例。人や文化的要素を含むものが一切描かれていない。
その日本に、明治の初め西洋の近代科学的なものの見方が導入された際、日本人の自然への眼差しには徐々に変化が加わります。特に西洋から導入された風景画は日本の風景を客観的、科学的に見直す機会となりました。レクチャーでは、雇われ外国人絵師として招聘されたフォンタネージの教育のこと、その日本人画学生達のエピソード、ジョン・ラスキンの「近代画家論」が日本に与えた影響、(ラスキンは当時の教科書に掲載されるほど日本では有名だったとのこと)、志賀重昂(しがしげたか)の『日本風景論』とラスキンの自然論との関係などの話を交え、日本の近代自然観が変容していった過程が分かりやすく説明されました。
渡辺先生は最後に、志賀重昂が日本の風景の素晴らしさを近代ナショナリズムに結びつけていったというお話で締めくくられていましたが、風景画さえも愛国心を養う手段とされた、大変興味深い例といえるでしょう。このようにして、近代日本の自然観への様々な興味も尽きない中、約1時間半にわたるレクチャーは終了しました。
<関連リンク>
・「ネイチャー・センス展: 吉岡徳仁、篠田太郎、栗林 隆
日本の自然知覚力を考える3人のインスタレーション」
会期:2010年7月24日(土)~11月7日(日)