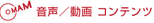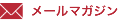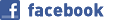いよいよ開催の「六本木クロッシング2010展」。そこで展覧会作りの専門職・キュレーターに、その見どころを直撃取材しました。その模様を6回に分けて連載します。登場してくれるのは、森美術館アソシエイト・キュレーターの近藤健一。第1回目は同展の成り立ちと、2010年版のサブタイトル「芸術は可能か?」に込めた想いを語ってもらいました。
――はじめに「六本木クロッシング展」の成り立ちを教えてもらえますか?
近藤:3年に1回、日本のアートシーンで起きていることを紹介するために、森美術館が開催している展覧会です。常に現在形のアートを紹介していく「日本アートの定点観測展」とも呼んでいますね。森美術館がオープンした翌年の2004年から始まり、今回で3回目です。
――まもなく始まる最新回は、どんな展覧会になるのでしょう?
近藤:「六本木クロッシング2010展」では毎回、館内のキュレーターと、外部からもゲストキュレーター陣を迎えて、共同で展覧会を作り上げていきます。開催ごとにその顔ぶれが変わるのも特徴ですね。今回は館側から私が、そしてゲストキュレーターとして大阪大学などで教鞭を執っている木ノ下智恵子さんと、国内外で展覧会を手掛けているインディペンデント・キュレーターの窪田研二さんを迎えて企画を進めています。その背景も表現方法も個性的な、総勢20組のアーティストが参加する展覧会になる予定です。
――今回のタイトル「六本木クロッシング2010展:芸術は可能か? --明日に挑む日本のアート--」には、どんな想いが込められていますか?
近藤:展覧会のコンセプト作りの段階から、3人で時間をかけて、どういう方向性にするかを話し合いました。そこで自然と出た話題が、アートバブルの崩壊後、いま私たちは何を考えるべきかということです。現代アート界にも、いわゆるリーマン・ショックの直前までバブル的状況がありました。それがはじけたいま、日本の美術館はどうなるのか、今後どうあるべきなのか。また「2000年代後半に起きた事って何だろう」と、アート界だけでなく一般社会のことも含めて話し合いながら、いま「六本木クロッシング2010展」で何を観てもらいたいかを議論しました。
その結果、単にいま活躍しているアーティストを網羅的に紹介するより、よりメッセージ性のある企画にするべきではという結論に達しました。そこでキーワードになったのが、本展のサブタイトルにもなっている言葉なんです。
――「芸術は可能か?」という問いかけですね。
近藤:そうです。これは、今回もそのパフォーマンスの記録映像を上映予定のアーティストグループ、ダムタイプのオリジナルメンバーのひとりで、1995年にHIV感染による敗血症で若くして亡くなった古橋悌二さんが残した言葉です。当時どんな意味でこの問いが発せられたかと言うと、彼いわく、何もかもが可能に見えた80年代に対して、90年代に入ると――バブル経済の崩壊と重なります――自分たちが生きるこの時代ならではの問題意識って何だろうかと、迷いが生じ始める。そんな中で、いま芸術に何ができるのか、と改めて考えたときに出てきた言葉なんですね。
アートがアートの枠の中に留まるのではなく、その外側にも影響を及ぼすことでこそ、芸術は成立するのではないか。そういう気持ちで発せられた言葉だったようです。

森美術館アソシエイト・キュレーター近藤健一
――この言葉を、2010年のいま、改めて問いかける意味とは?
近藤:まず、経済が停滞してアートの市場も影響を受けるという構図が、かつてのバブル経済崩壊後と色々な点で重なって感じられるというのがあります。こういう時代にこそ、アート本来の価値や存在意義が問われるのではないでしょうか。
また「芸術は可能か?」という問いは、より一般的な問いかけとしても、挑発的な意味を持つ良い言葉だと感じているんです。この問いから、いま2010年にアートに何ができるのかを、また、アートの可能性みたいなものを考えたいと思っています。
《次回、第2回明日に挑む日本のアート:クロッシング=交差に迫るキーワードへ続く》
<関連リンク>
「六本木クロッシング2010展」
会期:2010年3月20日(土)~7月4日(日)