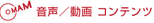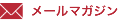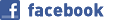2016年3月4日、東京、六本木の国際文化会館で「大惨事におけるアートの可能性」と題した国際シンポジウムが開催された。主催は筑波大学で、同大芸術系が中心となって2012年4月から行ってきた「多領域と芸術の融合による創造的復興に向けた人材育成プログラムの構築」(以下、創造的復興プロジェクト)が当初の活動予定の4年を迎えるにあたり、また、東日本大震災から5年の歳月を数えるにあたって、同プロジェクトの活動報告を行うとともに、大惨事とアートをめぐる様々な取り組みの事例紹介、意見交換などが行われた。

筑波大学による福島県大熊町のプロジェクト *1
登壇者は、窪田研二(キュレーター/筑波大学芸術系准教授)、飯田高誉(インディペンデント・キュレーター)、近藤健一(森美術館キュレーター)、ヤコブ・リルモーゼ(X AND BEYONDディレクター)、宮原克人(漆芸家/筑波大学芸術系准教授)、ジェイソン・ウェイト(インディペンデント・キュレーター)の6名。いずれもが、大惨事に関するアートプロジェクトに携わっている。司会を窪田が務め、飯田はコメンテーターとして各発表者のプレゼンテーション後にコメントを述べた。
第一部「事例発表」では、宮原、リルモーゼ、近藤、ウェイトの4名が、スライドを用いて自身が携わるプロジェクトの発表を行った。

宮原克人氏(漆芸家/筑波大学芸術系准教授)
第一発表者の宮原は「創造的復興に向けた人材育成プログラム」と題し、創造的復興プロジェクトの目的や4年間の活動内容、今後の展望や課題について報告した。本プロジェクトは芸術系に限らず、理工系、人文系など多領域の学生および教員が協働して行うもので、東日本大震災で被災した地域の多様なニーズに応えるとともに、災害などの社会問題に対して積極的に課題解決に取り組む人材の育成を目的としている。
活動拠点のリサーチから始まったプロジェクトは、仮設住宅の住民との夏祭りの開催や、被災者の日常化した非日常に焦点を当てたアートワーク、映画制作・配給会社とのドキュメンタリー映画制作などに発展。多様なプロジェクトの一端が紹介された。
宮原は、プロジェクトを通じて「教育は、社会やコミュニティといった学校外の場が担う部分が大きいことに気づいた」と述べる一方、震災から5年を経た今も仮設住宅に暮らす住民からは、元の生活を取り戻すことへの諦めに似た声も聞かれるなど、復興の難しさについても語った。
続く発表者のリルモーゼは、「大惨事について高度なリテラシー習得のプログラムを作る:X AND BEYONDのキュラトリアル・コンセプト」と題し、自身がディレクター兼キュレーターを務めるプロジェクト・スペースの活動を紹介した。

ヤコブ・リルモーゼ氏(X AND BEYONDディレクター)
デンマークのコペンハーゲンに拠点を置く X AND BEYONDは、現代社会におけるアートや大衆文化と大惨事との関係性の研究を目的に、展示や上映、レクチャーなどを企画している。一例として紹介された「Survivalist Toolshed(サバイバリストの道具小屋)」は、20組のアーティストが一律の金額で、大惨事において有用と思われる物を制作または購入した展覧会。避難のためのボートや、願いが叶う魔法の杖といった作品(道具)が展示され、会期終了後にはオークションを開催。売上を国境なき医師団に寄付した。大惨事という事象を、大衆文化と融合して提示する手法について、飯田は「非常に興味深い」と評価した。

発表を行なう近藤健一(森美術館キュレーター)
「紛争、時間、写真」テート・モダン、2012年
Conflict, Time, Photography © Tate Modern 2014-2015
第三発表者の近藤は、森美術館で「カタストロフィーと再生」をテーマにしたグループ展の企画を検討していることから、「美術展に見る大惨事のイメージ」と題して、自身がリサーチしてきた世界各地の美術展の報告を行った。
近藤は、調査にあたって「美術館における美術展」「時間の経過」「ショッキングなイメージ」の3つの視点から美術展を分析。大惨事の発生時において、チャリティオークションなどの即時的なアクションの必要性は認めつつ、美術館の本来の役割は、価値ある作品を展示、図録に収載し、言説として後世に残すことではないかと提言。また、事象の発生から写真として記録されるまでの時間をテーマにしたテート・モダンの展覧会「Conflict, Time, Photography(紛争、時間、写真)」(2014-15)の展示作品を例に、時間の経過とともに、表現が直接的なイメージから抽象的なイメージへ変化することを示した。美術展におけるショッキングなイメージの取扱いについては、表現された事象の加害者であるか被害者であるかなど、観客の持つバックグラウンドによってイメージの文脈が左右されること、米田知子の作品を例に、隠喩的手法であっても惨事を表現しうることを提示した。

近藤健一(森美術館キュレーター)
最終発表者のウェイトは、「Don't Follow the Wind:福島の帰還困難区域におけるアート」と題し、自身が共同キュレーターを務める「Don't Follow the Wind」展(以下、DFW展)について報告した。本展は、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故により、原則立ち入り禁止となった福島県の「帰還困難区域」で開催されている国際展。展覧会は2015年3月11日に始まったが、2016年3月現在、住民帰還の目処は立っておらず、避難指示が解除されるまで「観に行くことができない展覧会」である。

ジェイソン・ウェイト氏(インディペンデント・キュレーター)
展覧会には、国内外12組のアーティストが参加。その一作品として紹介されたアイ・ウェイウェイの《希望の光》は、住民が居住できなくなった家に太陽光発電装置を設置し、人がそこで寝起きしていれば電気がつくはずの朝と夜に明かりが灯る作品。かつてあった日常生活を想起させられる作品で、「想像力の喚起」というアートの持つ力について示唆に富む報告を行った。
第二部の「討議」では、まず飯田が青森県立美術館美術統括官時代に企画した「青森EARTH 2012」展について紹介。同美術館が有する戦後作家のコレクションをベースに、チームラボなど現代の作家も紹介した本展では、「ヒロシマとフクシマ」「危険社会」といったテーマの展示室を設けて展覧会を構成。核燃料再処理工場の立地県で、こうした展示を行うことの難しさを吐露しながらも、公共の場としての美術館の役割を会場に問いかけた。

飯田高誉氏(インディペンデント・キュレーター)

窪田研二氏(キュレーター/筑波大学芸術系准教授)
以上の事例報告を受け、窪田が各プロジェクトを①リサーチに基づきメタレベルで災害を捉えるアート、②惨事の現場に入り込んで実践するアートのふたつに大別。美術館やギャラリーで展示を行う近藤とリルモーゼの事例を①、宮原とウェイトの事例を②としたうえで、それぞれの見地から発言を促した。
近藤は、上映やレクチャーなど、多様な手段のひとつとして展示を用いるリルモーゼの事例と、展覧会ありきの美術館は正確には異なるとしながらも、多くの人が好きなだけ思索をしながら鑑賞できる美術館での美術展の可能性に言及。それを受けて飯田は、社会制度やコマーシャルな枠組みのなかでアートを実践する美術館の役割を再考するのに、大惨事は重要なテーマであると指摘した。
以前は美術館に勤務して①のアートを実践し、現在はDFW展など②のアートを実践する窪田は、作品の受け手が「鑑賞者」から「参加者」へ、より能動的に変化したとし、伝統的な芸術が「再現」であったとすれば、現在のアートは作者と参加者による現実の「創出」であると、社会とアートの変容について意見を述べた。
これらの討議を受けてウェイトは、“Radical imaginary(革新的想像性)”というキーワードを用いて、より広い視点でアートの役割について言及。革新的な作用を人々に与えることにより、人々の新しい生き方のヒントになり、新しい共同体を生み出すきっかけとなる、とした。
また、自分たちが何がしかの枠組みのなかでアートを実践していることにも触れ、そのなかで表現を行う以上、属する枠組みに呼応した表現になるのは自然なことであると指摘。DFW展はアブノーマルな形のアクションだからこそ、今も継続する原発事故に光を当てることができていると述べ、それぞれの枠組みにおいてアートを実践することの重要性を説いた。

左から、ウェイト氏、飯田氏、リルモーゼ氏、宮原氏
会場との質疑応答では、大惨事というテーマを扱う際の留意点や気付きについて質問が寄せられた。リルモーゼは、大惨事を扱うなかで自身も厳しい精神状態に追い込まれた経験を述べ、ウェイトは、当事者の私的な領域に立ち入るからこそ信頼関係の構築は欠かせないと回答。本テーマを表現することの難しさや、表現の前提についても共有された。

会場の様子
飯田は、大惨事を正面から受け止める登壇者らの姿勢に感銘を受けたと感想を述べ、直接の被害者でない者も被災地の復興を望んでいることを伝えつづけるためにも、このような取り組みを継続していくことが重要だとして、シンポジウムを締めくくった。
文:木村奈緒(フリーランス)
| 写真提供: | 筑波大学 © University of Tsukuba *1のみ、写真提供:宮原克人 |
<関連リンク>