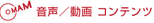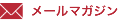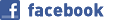日本の現代アートを幅広い視野から検証する「六本木クロッシング展」。展覧会ではいくつかのテーマを設定していますが、2016年4月25日に開催したトーク「アーティストは戦争とどう向き合ってきたのか」はそのテーマの一つである「過去との新たな出会い」に焦点を当てるべく、ドイツからウルスラ・シュトレーベレさんを招き、日本とドイツのアーティストがそれぞれ戦争や過去の記憶とどのように向き合っているのかを検証しようとするものです。

会場の様子
昨年は第二次世界大戦終結70年にあたり、私たちは日本の敗戦という過去を意識せざるをえない年でした。展覧会の準備段階であったそのころ、本展キュレーターチームの一人である荒木は、日本で活動する若いアーティストらが彼らなりの態度で戦争という過去に向き会う作品に興味をもち、展覧会で紹介すべく調査を重ねました。本展覧会に出品している彼らとドイツのアーティスト達とを比較してみたとき、そこにはどのような共通点、もしくは差異が見られるのでしょうか。

後藤靖香 《寄書》
2008年
まずは、荒木から本展出品作家の中から、戦争にかかわるテーマを取り上げる作家を紹介しました。
例えば後藤靖香は、特攻隊員だった自分の祖父や親戚から聞いた戦時中の話を題材に「戦争画」を描いている作家です。「軍人」とひとくくりにするのではなく、彼らが個人として何を考えどのような日々を送ったのかを後藤は絵画という形態で表現しようとしています。悲惨な戦場を描くのではなく、戦時下の人々の語られない声を捉えようとしています。

藤井 光
《帝国の教育制度》
展示風景:「六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声」森美術館、2016年

佐々 瞬 《旗の行方》
2016年
藤井光は本展のために、1940年代に米国が敵国研究のため日本の教育制度を取材した映像と、昨年藤井自身が韓国の学生達と行ったワークショプの様子の映像を組み合わせて新作を制作しました。日本帝国主義下で教育された日本の子供たち、現代のソウルの大学で教育をうけている韓国の学生たち。帝国主義と教育という仕組みについて身体の動きや表情を通して考えさせられる作品です。
佐々瞬は「暮らしの手帖」の編集長だった花森安治に焦点を当てる映像作品を出品しています。花森は戦時中に戦意高揚のための広報活動で大政翼賛会に加担してしまったことへの反省から、戦後は庶民の味方となり消費者目線を大事にする『暮らしの手帖』の基礎を作り上げました。映像の中で佐々自身が花森に扮して、つぎはぎした旗を振っています。これは『暮らしの手帖』の読者の女性達の思い出の布からつくられた旗を縫い合わせたものです。この旗を振る行為は、権力に振り回されず自分たちの旗を振るべきだという花森の主張を体現しているようです。
他にも、原子爆弾と放射能を主題にインスタレーションを制作した小林エリカ、映画『ヒロシマ・モナムール』へのオマージュ的作品で罪と許しをテーマにしたジュン・ヤン。沖縄出身のミヤギフトシの作品には、アメリカの占領を経ていまだ多くの土地が基地に占められている沖縄の現状が見え隠れします。

荒木夏実(森美術館キュレーター)
ここに取り上げらたアーティストは40代以下の若い世代ですが、彼らは「戦争」を悲惨なものとして捉えるだけではなく、現代に生きる自分に引きよせて、戦争が何をもたらしたのかを理解しようとしているように思えます。彼らの表現行為には、語られてきた「戦争」をそのまま鵜呑みにするのではなく、大きな物語に隠されて語られない部分を、静かに掘り起こそうとしているように捉えられます。荒木の丁寧な説明から、上記のように感じられました。彼らの作品は、決して声高に戦争への反対意見を表明するものではありませんが、それは歴史に対する彼等なりのアプローチの方法といえます。

ウルスラ・シュトレーベレさん(ベルリン芸術大学美学美術史博士課程在籍研究員、作家、キュレーター)
次に、ベルリン在住のウルスラ・シュトレーベレさんが、戦争という歴史に対してドイツのアーティストはどう向き合っているのかを概観し紹介してくれました。シュトレーベレさんは近現代彫刻の専門ということで、古来彫刻という芸術形態がその耐久性や荘厳性から教会や為政者の権威誇示に結びついて制作されてきたこと、近現代ではそれが国家や英雄、戦争や平和の記念碑へと引き継がれていることなどをフリッツ・クレマー《ブッヒェンヴァルトの記念碑》(1958)やベルンハルト・ハイリガー《炎》(1962-63)などを例に示しながら説明しました。

フリッツ・クレマー《ブッヒェンヴァルトの記念碑》1958
(ブッヒェンヴァルト強制収容所の犠牲者への追悼のためのもの)
Quelle: Foto Peter Hansen, Sammlung Gedenkstätte Buchenwald
シュトレーベレさんは、ドイツの現代美術の第一人者であるヨセフ・ボイスを抜きには、やはり戦後ドイツのアートは語れないといいます。彼はドイツを代表する現代美術家であるだけでなく、思想家または社会活動家でもあり、世界中のアーティストに大きな影響を与えた人物です。
ボイスは、第二次世界大戦従軍時にクリミア半島を飛行中に撃墜され、重症を負ったところを遊牧民に助けられ体温保存のために脂肪をぬられフェルトにくるまれたという経験から、脂肪とフェルトを作品の素材として頻繁に取り上げます。作品の根底に、自身の戦争体験があることが意識され、また自国の犯したホロコーストという負の歴史がその後の活動に少なからず影響を与えているとシュトレーベレさんはいいます。また、ボイスは作品制作だけでなく、「自由国際大学」の設立や、環境保護など、その活動はアートの範疇を超えて社会へと広がり、彼が提唱した「社会彫刻」(だれでもが想像力を発揮すれば、より良い社会を彫刻することができる、変えることができる)という概念は、現在でも若いアーティストに影響を与えていることが語られました。

ボイスに師事したアンセルム・キーファーや、同じくドイツの作家であるハンス・ハーケも、ナチス・ドイツに切り込む作品を多数制作しています。例えばハンス・ハーケが1974年に発表した《マネ・プロジェクト》では、美術館に寄贈されたマネ作の絵画《アスパラガスの束》の来歴を詳らかにすることによって、この作品がもともとはユダヤ人の所有であったにも関わらず、元ナチのドイツ人が寄贈者であることを明らかにし、寄贈という行為が過去の罪の隠ぺいにつながることを表出させました。この作品は大きなスキャンダルとなり当時展覧会への出品が差し止められたとのこと。また同じくハーケが1993年のベニス・ビエンナーレで発表した《ゲルマニア》は、ビエンナーレ会場のドイツ館に残る、ヒトラーに所縁のある大理石の床材をひきはがし、粉々にして瓦礫化するというセンセーショナルな作品でした。
彼らの作品は時に挑発的で物議を醸し出すものですが、このように、作品をもって社会に問題を投げかけ、議論を引き起こそうとする「社会彫刻」につながる概念は、現在の作家にも十分に引き継がれているとシュトレーベレさんはいいます。

ドイツは第二次世界大戦での敗戦後、40年にわたり東西分断されたのち再度統合したという歴史があります。シュトレーベレさんのレクチャーからは、この複雑な歴史を経てきたドイツでは、戦争や東西冷戦だけでなく、昨今のEU統合にまつわる問題、難民問題、経済・政治に関わる様々な問題に対し、自らの意見を表明することが、アーティストとして当然のことと捉えられていることが分かりました。例えば、現在ベルリンで活躍するTHE ARTIST COLLECTIVE CENTER FOR POLITICAL BEAUTY は、アートと政治的活動とを結び付けようとする作家集団ですが、《White Cross(白い十字架)》(2015)や《The Deads Arriving(死者の到着)》(2015)というプロジェクトでは、現在急増している難民の問題に言及し大きな話題となりました。「白い十字架」とは、東西分断時にベルリンの壁を越えようとして命を落とした人を悼む十字架で、ベルリンの壁があった場所に置かれていたものですが、彼らはそれらを取り外し別の場所に設置するという手法で、社会の緊急課題である難民問題へと人々の目を向けさせました。また、《The Deads Arriving(死者の到着)》 では国会議事堂の前の広場に疑似的に墓をつくり、多くの難民達が死に瀕していることを視覚化させたのです。ある種不快感をも伴う彼らの作品ですが、人々の感情に摩擦を起こすことよって感情だけでなく思考や理性にも訴えかけうる力を発揮しています。彼らによれば、このように社会問題を取り上げる作品は、必然的に見る者に痛みを強いるものであり、同時に挑発的であるべきだとも考えているとのことです。

THE ARTIST COLLECTIVE CENTER FOR POLITICAL BEAUTY
《White Cross(白い十字架)》
2015年
© weiße Kreuze: Ruben Neugebauer

THE ARTIST COLLECTIVE CENTER FOR POLITICAL BEAUTY
《The Deads Arriving(死者の到着)》2015年
© the dead are coming: Nick Jaussi
日本では戦争や歴史問題を取上げる作家はいるものの、このような過激な作品は多くはないように思われます。ディスカッションの中で、日本では、戦争を取り上げる以前の問題として戦前戦中にそこで何が起こったか、なぜ起こったのかということを若い世代は知らない、知らされていない、という現状があるのではないかという意見がありました。もちろん戦争の悲惨さは語り継がれていますが、日本では戦争責任や植民地行為についてはタブー視される部分も多く、それに触れることを躊躇する空気も濃厚です。東京都現代美術館では、表現規制や圧力に焦点をあてた「キセイノセイキ」という展覧会が行われていましたが(会期:2016年3月5日-5月29日)、シュトレーベレさんによれば、ドイツのアーティストは社会の問題に対して意思表明することになんら躊躇することはなく、自主規制をかけることなどは考えられないといいます。 ドイツでは学校教育の中にナチス・ドイツで何が起きたのかを教えるカリキュラムが組まれており、否が応でも自国の負の遺産について考えさせられる機会が多いという現実があります。そのような機会に政治的倫理的問題に取り組む姿勢を訓練されることは、その後の社会に対する姿勢につながっていくのかもしれません。
過去の歴史をどう捉えるかという問題は、現在の社会と作家の関係の有り様をも考える機会になりました。
文:田篭美保(森美術館シニア・コーディネーター)
撮影:永禮 賢(展示風景)、古川裕也(イベント)
<関連リンク>
・六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声
会期:2016年3月26日(土)-7月10日(日)
・関連展示「MAMスクリーン003:交差する視点―海外アーティストたちが見た日本の風景」
会期:2016年3月26日(土)-7月10日(日)
・アーティスト×キュレーターによるセッション
「六本木クロッシング2016展」クロストークDay 2をレポート
~藤井光、佐々瞬、高山明、ミヤギフトシ、百瀬文、志村信裕、山城大督